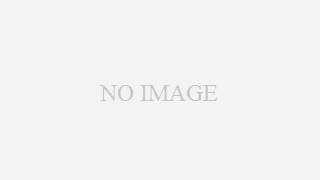巨大なクレーン車が何かの具合で十字架に見えた、青空に鉄の十字架が見えると子供は教室の窓から外を見て思っていた。
「おい!みんな何やってるんだ!仲間外れにして可哀そうだろ!!」教師の怒号が飛んで、それまで自然に友達同士で輪になっていた子供らは硬直して一人を見つめた。その子供は教室の隅の席に一人で座って、広げた本を見ずに宙を見つめているばかりであった。教師は怒鳴った。「今は自由時間だろ!自由時間にはみんなで、み、ん、な、で!遊べとあれほど普段から先生言ってるよね?!仲間外れにするな!!」子供らは、さて誰がこの除け者に話しかけようかとそれぞれに目配せし合って無言のうちに会話していた…男子が話しかけなよ男の子なんだからあいつ、えーやだよあいつ無口なんだもん女子が面倒見ろよお前面倒見いいだろ?…この会話は無論当事者の除け者、もとい、余り者、余計者である少年にも伝わっていた。しかし口が動かなかった。少年は黙って彼らの会話を見つめていたがおずおずと手を挙げた、先生に何か意見を言うためだった。皆固唾を飲んで見守っている中少年は言った。非常に聞き取りにくい声で…慢性鼻炎のためか時々に痰を飲み込みながら話した(その都度女子たちは表面上は笑顔のまま顔をしかめていた)「あのう…俺は…本を読んでいるので…」教師は少年の返答に対し即答して言った。「本?何の本だ?みんな注目!本を持ってきているみたいなので、何の本を読んでいるのか、どんな話なのか教えてもらおう!」無口な少年は演劇の本を必死で隠した。物語や舞台では誰もが誰にでもなれる…自分以外の誰にでもなれる、少年はいつも夢想していた、自分以外の誰かになる夢想を…そして異なる立場を共有するという夢想を、誰にでも語り掛け、話しかけるという夢想を必死で隠した。
少年の受けたこの種の苦難はまさに言葉にしがたいものであった。
…それは義務教育中続いた…というものを有体に言うならば、人間社会へと強制的に参加させられ、また自身の人間社会不適合さを常に指摘されていたことだろうか、この少年が自分の内面を他人に知られるのを次第に極度に否むようになったのは無理からぬ話であった。学校で強制的に行われていた放課後の『クラス遊ぼう会』もこの寡黙な少年には拷問に思えたし、普段の学校生活も彼からすればほとんど刑務所生活と同義であった。帰宅すれば帰宅したで両親に今日の出来事を報告せねばならなかった。父は怒りっぽく、少年がどもるたびに怒鳴りつけた。「いいか!普通に勉強だけしてたらお前は社会の屑になるぞ!フリーターなんかなるんじゃないぞ、あんな奴らは自業自得で低所得者になったんだ、今からやるんだ!今から勉強しておけばお前は生きていける!英語をやれ!ほら、昨日教えたところは…なんで喋らないんだ!英語で自己紹介してみろ!!」
この両親の家庭教育の賜物か、合わぬ学校生活で絶えず対人関係の苦手さを克服すべしという精神的激励が続いたせいか…少年が青年になる頃には、異なる立場を共有し語り掛けるという夢想を抱いている彼は皮肉にも吃音障害を抱えるに至っていた。
英語どころか日本語の発音さえ危ういこの役立たずを、なんとか殴らないように殴らないようにと父親は怒りを堪えていた。訓練のためにとアルバイトに精を出しても、どもりのせいで同年代の若い同僚たちには漠然と避けられた。シフトで組んだ女の子がバックヤードで嘆いていた。「あたしあの人苦手~」俺もだよ、俺も自分が苦手だし大嫌いなんだ、それに君のことも苦手だと彼は落胆しながら心で返答していた。不思議と心の中での会話には彼は躓かなかった。相変わらず鼻水を垂らして生きている彼はティッシュとハンカチを常備し、トイレでは尿道と鼻から水分を絞り出し、心ではいつも泣きながら生き延びていた。この哀れな青年はいつしか成人したが、彼は絶えず救いを求めていた。彼にとって救いというのは、何も女といちゃいちゃしたいとかそんな事ではなく、ただただ人間として生きている喜びを感じられる毎日を送りたいという静かな静かな希望に過ぎなかった…これは切望であった。この切望が男の中で膨れ上がるほどに男は、いつしか頻繁に自殺することを考えるようになっていた…。
喋れるか喋れないかというのは人間として生きることが可能なのかそれとも不可能なのかという感じがすると男は思っていた。心の奥底で男は常に問うていた。何故自分はこんな風に生きているのか?苦しみには何の意味があるのか?具体的にこの苦しみを回避するには喋る特訓をするより他なかった。キリストは言う…『神の御業が現れたに過ぎない』人生のはじめのうち吃音が無かったことを考えると訓練で何とかなりそうだと思った男は声が隣家に響かないように配慮して、暗い部屋の中にあるクローゼットに籠って発音の訓練をした。仕事先でうまく挨拶が出来ないと失笑された。「あの人って何なの?あああんまり触れちゃいけない系の人?」男より若い人間は彼を嫌悪し、年配者は嘲笑し、人には誤解された。「最近の人って挨拶も出来ないのね嫌になる、うちの家族の子供たちはちゃんと挨拶するのに、子供でも出来ることを社会人になってもやらないんだから」他にもいろんなことを言われていた。「彼女居ないの?あ…居ないよね」「え、すみません、今なんて言いました?聞こえなくて、もう一回言っていただけます?」「あの人怖い、いつも怒ってない?」「もうちょっと頑張りなよ」「もっと大変な人だっているんだよ、治そうって思ってる?」
み、ん、な、というのはどこにいるんだろうと男は思った、舞台やお芝居で人間同士の見せる美しいもの…ああいったものを作り出すみんなはどこにいるのだろう?
この男にとって人間であることの利点と言えば話し話される劇中に飛んで行けるということだけだった…喋りたいのに喋れない男の求める演劇…これだけは幼少期からの変わらぬ趣味だった。その一方で出来れば自分の発音や自分の声など一生聞かずに一生喋る機会から逃れて山奥で暮らしたいと何度も願った。それを願えば願うほどに切望は膨らみ、男は無力さにつぶれないようにと自らの感情と真逆の行いを自らに課した。自分の発音や発声に耳を傾け、毎日毎日ひたすらに訓練したのだ…。その努力を知るものは誰も居なかったが男は鏡に映る自分を孤独な仲間と見なして仕事の合間に訓練していた。そして丸一年が過ぎるころには多少つっかえつっかえではあるがなんとか話せるようになっていた。吃音持ちとはいえ、あるいは喋ることに抵抗があったからこそ密かに強く強く演劇を好んで鑑賞していた男が素人演劇教室へと足を運んだのは傍目には奇異であったが本人とすれば至極当然の流れであった。彼はもういい加減別の人間になってみたかったのだ。
演劇教室は本当に素人だけの集まりで皆ド下手であったので男は非常に安心していた。講師の老人は朗らかに言った。『活舌や発音は練習です、練習あるのみです…』それをいたく実感している男は静かに頷いた。やがて台本が配られ、大人しい男という役を演じていたこの男に講師は言った。『うーん君は…悪くないよ、発音を気にしているのかもしれないが』講師は吃音の少しあるのを察してかそれに触れないように指摘しつつ続けた。『それでも自分なりにやればいい』男は安心して大人しい男を演じきった。そして次の台本が配られた…男は当惑してかつて子供時代に教師にしたのと同じようにおそるおそる手を挙げて統率者である講師に発言した。「…す、すみません、やれる役がありません」『やれる役が無い?役はたくさんあるじゃないか』講師は続けて言った。男は朴訥とした風ながらも反論した。「だって…口達者ないじわる婆さん、着飾った娼婦たち、酔っ払いの極悪人、とんでもないプレイボーイ、王様、イエスキリスト…共感できる役がありません…俺は男だし…でも俺は、自身の経験としては、酒も嫌いだし、女性ともそんな…あの…、王様でもないし…イエスキリストは違う感じがするし」男は講師を見つめて懇願した。他の素人演者たちも大いに共感し頷いていた。男はそのせいもあって精一杯抗議した。「お、男なので…女性の役は…女性っていうのは…俺には遠い感じだし、こないだのあの役、大人しい男、あの役は自分の経験を活かせたので演じることが出来たんです…未知の役をやるのはちょっと」
『そうか…台本はまだある』老講師は何か意味ありげに微笑んでもう一冊の台本を皆に配った。無口な男はまた動揺した。登場人物はいつも怒っている非常に厳しい父親、元気溌溂でデリカシーの無い教師、排他的な子供たちや人々、うわさ好きの女たち、冷ややかな同僚…男は首を振って言った。「あ、あのう…これは…」皆も何か個々人の人生に於いて嫌な思い出を刺激されるらしく黙っていた。学園物はやりたくないとか、親が厳しかったからその悪夢を連想させるものを敢えて演じるのはきつい、そんな声が上がった。老講師は静かに言った。
『皆さん、人生で敵だと思った人物像を知りたいと思ったことはありませんか?』
『あるいは』老講師は続けた。『未知』老講師はいつものように朗らかに笑い、改まって皆に講釈した。『演劇のいいところは、何にでもなれるということなんです、舞台上では誰でもなんにでもなれるんですよ、王侯貴族や天才!男や女、紳士淑女はおろか下品な連中にまでなれるんです、敵にだってなれるんですよ、別に厳しい親が敵っていうわけじゃないんですがね、それでも一人の人間がぺしゃんこになるくらいの悪事を気付かずに働いてしまっていることが人間には往々にあるんです、それを気付かない人間というのが世の中にはごまんと居ます、一見正義に見えるような暴力行為を行ってしまう人に私自身、なっているかもしれないし、またそういった人物に悩まされたりもしました、でも』皆は聞き入っていた。『…芸術だけは別ですよ、個人が日常の役柄を脱して異なる視点に瞬間移動することが可能なんです、だから芸術に於いては、この世の全ての人と異なる立場を共有することが可能なんです、舞台の全員の立場を共有することが可能なんです、ね?すごいでしょう演劇って…皆さんにはぜひ、一番、普段の自分自身であったら共感しにくい役柄を敢えて演じていただきたいと思います、ここは演劇団ではありません、演劇教室です、完璧に役をこなす必要なんかないんです、だからどうか、皆さんにはぜひ、汝の敵を知ろうという視点を持っていただきたい、敵とまではいかずとも、汝の未知を知ろうとしてほしい』
男は打たれたように老講師を見つめた。講釈を終えた老講師は言った。『君は…女性の役でもやるといい、そうだなうわさ好きの女の役をやるといい』男は自宅のクローゼットで練習に励んだ。「あの人こわい~、あの人、あたし苦手、彼いつも怒ってない?」
次の役は意地悪な老婆だった。「まあやだ最近の人って挨拶も出来ないのね嫌になる、うちの家族の子供たちはちゃんと挨拶出来ますよ、子供でもできることを大人になってもやらないんだから、ああ、昔の古き良き時代が懐かしいわあ」
今度は娼婦。「あんたみたいなの相手にしてるんだからいつもよりも多めに支払ってよ」世話好きの女房「え?何て言いました?お兄さん声が小さいから何言ってるか聞こえなくてあっはっは」
自称善人。「もうちょっと頑張りなよ!もっと大変な人だって頑張ってるんだ、君になら出来る!」
これは大役、イエスキリスト。「神の御業が現れたに過ぎない」
プレイボーイ。「うん、初めてだよ!あの子と寝るのはね」
…台本は月ごとに変わった、はじめのうち非常に強い苦痛すらも感じていた男はある日演劇中にふっと景色が違って見えるようになった。それは自分が女の子の役柄を演じている時のことだった。頭では、女の子というものは男よりも小さくて、自分は背が高い方であるから女の子の役を演じるには背を屈めなくてはならないという思いに捉われていたが、唐突に景色が開けた。自分は兄の手を取って駆け出していた、大丈夫よお兄様私がついているから…あの丘を越えて星空の向こうに行けば大丈夫、そこには神様がいらっしゃって私たちを見ているわ、だから逃げましょうお兄様…その時男は確かに星降る丘に兄と居たのだ。
兄は言った。「でも、父さんに見つかったら俺たちは殺される」妹であるところの男は言った…。『ううん大丈夫よ、お父様も分かってくださるわ、お父様だってお兄様が嫌いで叱りつけているわけではないんですもの、丘の向こうのあの星空の一粒の輝きになりましょう…いえ、やはりお兄様はおうちにもどってらして、大丈夫、私ちょっと天まで行って神様にお話ししてくるわ、お兄様が本当に思っていることがお父様に伝わりますようにって…』劇中、妹は星になり、今でも空から兄を見守っているというところで閉幕となった。無口な男はいつしか泣いていた。自分が何故泣いているのか理解できずにいたが確かにその時、男は女の子になっていたのだ。兄思いで父思いの女の子に…その役を演じているときに舌にかけられた呪いが解けたような気がして男は不可思議な感覚に包まれていた。役柄というのは確かに空想なのだがそれを演じた時にはここに居るのだ…男は老講師に聞いた。
「先生、俺は自分が…自分っていうのも何だか一つの役柄みたいな気がしてきました…」
無口な男は鼻をすすりながらも老講師に続けた。「今まで自分は、自分っていう殻の中に閉じ込められていて、そこから抜け出せないと思っていました、どんな時でも俺はうまく喋れない情けない男で、それが一生ずっと…一分一秒の隙間もなく続いていって、その間別の人間にはなれっこないんだなって思っていました…でも今俺は確かに、別の人間になっていました、それは俺の空想なんだろうけど俺は…とんでもなく自由です、空を飛んで星になりましたさっき…本当は、俺、こんなに自由だったんだって…思って」男は涙をこぼしていた。老講師はにっこりと笑みを浮かべて生徒を見て言った。『世界は空想で出来ていると思わないかね?世界は、見たことの無いもの、自分の知らないものの視点に飛んでいける人があれやこれやといろいろなものをこさえて、そうやって出来ているんだ、勿論それが物理的な発明だったりしたらすごいけれども、本当は皆…発明も芸術も同じなんだと私は思っているよ、世界中古今東西の人や生き物あらゆる存在の視点に、人間は移動することが出来る、だから見たことの無いものを作り出せる、これは想像力と呼ばれるが本当はそうじゃない、自力で作り出すのではなくて自分の魂というか、視点を飛ばすだけの話なんだ、舞台の登場人物の視点に移動するだけの話だよ、そうすればいろんな楽しさを受け取れるし、苦しみも受け取れる』
共有することだよと言って老講師は軽く肩を叩いた。帰り道に無口な男は考えていた。役柄を変える毎に生まれ変わるような新鮮さを感じていた…今の自分が死んだらこれも一つの役柄のように感じることが可能なのだろうか?この役柄はもうこの世に居なくなるけれども、それを演じていた自分と言うものは死後別の役柄を演じるのだろうか?今の役柄には似ても似つかないような、全く共感できない、または完全に未知の何かになるのだろうか?あるいは自分という存在もまた誰かにとっては完全に未知の、そして独自に重要な役柄なのだろうか?演劇と毎日の活舌訓練、そしてこの演劇中の神秘体験によって男は以前よりもずっと話しやすくなっていることに気が付いた。そして以前ならば嫌味にしか聞こえなかった励ましや種々の言葉も、誤解や、小さな悪意によるものだと理解するようになっていた。さな悪意が起こるのは本人の心の中に自分を認めてほしいという純粋な気持ちがあるからだということも…そしてそれが実は大抵、彼ら自身の両親に向けた欲求ですらあるということをも、劇中に悟っていた。老婆の中には小さい女の子がいつまでも居て自分はこんなに頑張っているのだと訴えており、プレイボーイの中には誰か永遠の一人を求める気持ちがあって、一見排他的に見える子供たちにはそれぞれに排除されたくないという恐怖が宿っていたことを理解していた。小さな女の子がまるで聖母のような慈愛を持っていたりもする。厳しすぎる父親、癇癪持ちの父親の中には自身への叱咤と謝罪とが含まれているのを体感した…男は空を見上げた。ちょうどそこには巨大なクレーン車がそびえ立っており、何かの具合で十字架に見えていた。素人とはいえすっかり雄弁な演者となったこの男は、冬の鉄の十字架が汝の敵を愛せよと大きく高らかに叫ぶのを横目に、笑顔で歩いて行ったのだった。