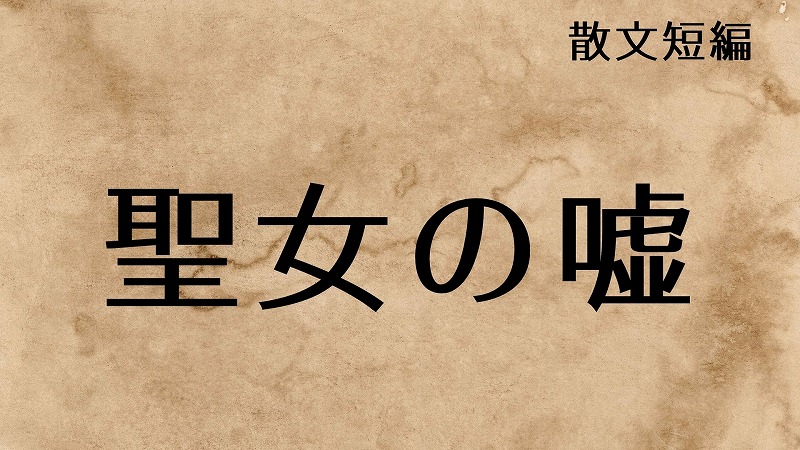琥珀と、極彩色の夢が見られる植物の原産地…そして十字架と骸骨が融合する小さな国、酸素の薄い高地の街の広場には、昼間っから酒を煽る男や、日がな一日骸骨の聖母に捧げる祈りを上げる住処を無くした哀れな老婆や、行くあてのない襤褸切れのような人たちが鎮座していた。その吹き溜まりめいた広場の中央には、スペイン軍が古代遺跡をレンガで固めた帝政時代に造られた噴水後地が恨めし気に残っていた…枯れてしまった噴水、あるいはかつての侵略王を讃える噴水など街の恥だとでも言うかのようにその小規模建築は土で埋め立てられ、早、大きな棺桶の様相を呈していた。
死を連想させる棺めいた枯れ噴水、こんな異物が街の広場中央に長年座していたのだから、この場所にカルテル同士の抗争の果てに惨殺されたと思しき切断遺体が鎮座されても閉鎖的な街の住民はそれほど驚かなかった。そもそも中央広場とその噴水跡地…普段からこの場所は不必要とされる物や人が最後に吸い寄せられるようにたどり着く世の果ての一点であったからだ。それでもこの暗い建築物が何処か街の運命を暗示したもののようにも思え、とんでもなく淀んだ雰囲気を醸し出してはいた。…この街はもう駄目だ…何よりも住民は運命を理解していたし、この摂理について口出しする者も、関与する者も皆無であった。
観光客はこの山岳の街や夢の葉に神秘を見出すが、土産物売りや街の露天商の女たちが皆民族衣装に身を包むのも第一には金のため、第二には一種の無関心さ…新しいものや外国といった外部への完全な諦念、そして我が身への無関心さを体現するための手段でしかなかった。
さて、とある男はこの街で生まれ、男の両親も神秘の植物を育てる農園を営んでいた。表面上は件の植物はこの街では原価で取引されるが、農園に直接加工を頼むために国を横断して内密にやってくる麻薬カルテルの人間も居た。そしてこの頼みは往々にして脅しであった…断ればカルテルの敵になり、受け入れれば街の裏切り者となる…。たいていの場合何とか交渉して何割かをカルテルに回し、残りを何食わぬ顔で街に売りに行く、この男もそうやって生きてきたしおそらく彼の息子もそうやって生きてゆくのだろう、男は内心思った『この街には悪人しかいない』
件の惨殺遺体は噴水跡地の土留めの中にまるで植物を表すかのように『植えられて』いた。手足は四方に土から生えてきたようにささっており、胴体は輪切りにされ、頭はその中央で花が咲いたように血だらけになって土の中に首から立てられていた。『この街は死者の街なんだ』確かに男の本音通り、この土地は古くから骸骨を奉る信仰があり、死そのものに儚い命が宿っているという考え方が浸透していた。だから命が絶たれるから死に至るのではなく、命というものが吹き消されて死という状態に戻ったのだと人々は感じ、死体がそのように中央広場で残酷に弄ばれようとも無関心であった。生命そのものが死の一時的な神の遊びに過ぎないのだ…それでも男は思った、誰も、警官さえも噴水跡地で嘲られ続ける死体をなかなか片付けようともしなかったことに男は憤っていた。『自分さえよければ他は関係ないのだろうか』しかし当の自分さえ…自分の親族の保身のためにあくせくと働くこの男でさえ惨殺死体に触れたいとは思わなかったし触れられないで居ることを悔しく思った。埋葬出来ないでいる自分に腹が立った。汚れたままで漫然と過ごす自分を心の内で叱咤していた。数日後に、おそらく一番下っ端と思われる警官が死体を片付け、さらに末端と思しき清掃人がその場を乱雑に清掃するのを見ていた男は身震いした…このまま無関心でいたら、またあの場所に死体が捨てられるのではないだろうか?本当に、街の中心地である広場や噴水跡地が日常的にごみ溜めとなってしまうのではないだろうか?
人間が崇高だと思う存在とは、人間を必要とせずに存在していられる何かである。男の祖母は話した『昔はね、水源だってこの辺にあったんだよ、それを政府の奴らがみーんな、持ってっちまった、一晩中捥いでも捥ぎきれないくらいの果物が生ったもんだ、ああ、あたしらの緑の楽園…あれこそが一番守るべきものだった、つまり土と植物だよ、植物こそは神様が一番に、生めよ、増えよ、地に満ちよとお示しになった尊い生き物なんだ、植物を人間があれこれ加工した馬鹿げたオモチャじゃなくて、植物そのもが一番秀でた生き物なんだよ、人間は馬鹿ばっかりだからそれを忘れちまったんだよ』
男は日々繰り返される祖母の話を一種の音楽と思って聞き流していたが、この日に限って彼女の言葉に何らかの光明が宿っているのを感じ、はっと顔を祖母の方へ向けた。皺だらけの老女は山の斜面に沿って作られた段々畑…というよりも神秘の葉を茂らせる木が延々に植えられた人工的な植林地をぼんやりと見ていた。節くれだった手にはすっかりすり減って丸くなったガラスのロザリオが握られており…それを繰りながら彼女は、聖母マリアへの愚痴とも祈りともつかぬ伝言を口の中でぶつぶつやりはじめている所だった。涼しい風が吹いたが、地面は干からびている。しかし水は残っていた…食料用には適さない農耕地の残り水がタンクの中に余っていたし、再生土も余っている、ふいに男は口を開いた。「ねえ婆ちゃん、水や土を街に施したら…俺は偽善者だと罵られるだろうか?」老婆は聖母マリアへの一方的通信を中断して孫息子に言った。
『坊や、偽善者だと罵られるのが嫌だというのなら何一つ出来やしないよ、かわいい坊や、お前も髭なんか生やしちゃって、何しようってんだい?』
「あの広場の噴水跡地に、うちの農園の余りの土を入れて、花壇を作ろうかと思って」
『聖母マリアさま!!…ああ坊や、きっと喜ばれる!!でも質問されることもあるねえ、第一に政府の許可を取っているのか、第二に、お前はどこのカルテルと通じてるのか』
この土地では何処の教会ボランティアをしているのかとはまず聞かれないだろう…教会の代わりにカルテルと聞かれるのだ。男は歯噛みした、実は政府に問い合わせて中央広場の噴水跡地に手を加えていいか確認してあった。答えは実に玉虫色で、止めろとも言われなかったがぜひやってくれとも言われなかったのだ。幸いにもそこの職員の名前までもをきちんと記憶しているのでこの点について質問されても窮することは無いだろう、問題は第二の質問だ…。厳密に言うと男は二つのカルテルに神秘の葉を流していた。その二つは表面上は和睦状態にある…あの死体がどこの誰かもわからないためにどのカルテルの仕業かも不明であったし、考えれば考えるほど疑心暗鬼に囚われた。
絞り出すように男は言った。「婆ちゃん、政府には話してある…良いとも、悪いとも言われなかった」老婆は中年の孫を見て微笑んだ。男が黙っているのを見ると独り言のように呟いた『街の中心広場がごみ溜めじゃあこの街は遠からず終わる、今よりもっと腐敗するよ、勿体ないね、せっかく聖者様が信じる者たちを連れてきて住まわせたのがここの始まりなのに…本当は誰かが何とかしなくちゃいけない、でも見て見ぬふりさ、あたしだってそう』
男は言った。「俺は…世界を良くしていきたいんだ、けど…現実は…もしあの枯れ噴水を花壇に改造して、それが元で、カルテルの奴らをあざ笑ってるって思わせちゃったりしたらどうしよう?」祖母は高らかに笑った。
『花壇で?坊や、花を見て喧嘩が起きるってのかい?金なら争いが起こる、花は人間が居なくっても咲くんだよ、植物ってのは人間なんかを必要としない、だからどんな人間でも植物そのものを有難がるんだ、金や宝石という【考え】が無くたって生きていけるけど、この地球に植物が居なかったら人間は生きていけやしないんだ!だから花を植えて嫌がられるなんてことは…まあまず無いんだよ、他人の家にどでかい花を植えるってのなら考えもんだけどさ、あの汚らしい噴水跡地を綺麗な花壇にしようってんだろ?あたしゃ100年近く生きてきて植物を心底嫌がる人間を見たことが無いよ…ま、この街に住んでたら臆病になるのは仕方ないけどね、坊やが死んでも、お前にはちゃんと息子が居るだろう?万一のことがあってもあたしが育ててくよ…孫息子のお前を育ててきたのと同じようにね…聖母マリア様がちゃんと見ててくださるよ、生きていても死んでしまっても』
翌朝、男は意を決して街の中心地へ赴いた。帝政時代はおろか祖母の時代には街は共産主義に傾いていた。その頃の感覚で言えば公共の場に一市民が造作を加えるなど言語道断だろう…。男は自分自身にも賛同の声と批判の声があがるのをまざまざと感じていた。俺は共産主義者だったのだろうか?…俺はとんでもないおせっかいをしに行くのだろうか?おせっかいどころじゃなく公共物に勝手に花を植えるなんて図々しいにも程があるんじゃないか?きっと沢山の人から咎められるだろう…だってこの街の人たちは、自分の領域以外に手を出すことを悪と見なしているのだから。それがスペイン移民以前からの文化なのかもしれない。今でも自分の所属するカルテル以外は悪、自分の親族以外は助けない、変化しないことを良しとしているのだ、自分自身さえも…。たとえごみ溜めになっているところを片付けたってお礼どころか文句さえ言われかねない。元の通りにしておけと言われるのを男はしきりに想像し、またその負のイメージを振り払おうと藻搔いたが無駄であった…土と水と植物を乗せた小型トラックを運転し、それがのろのろと広場に着いてしまった時、一斉に皆がこちらを振り向いたような気がして男はぎくりとした。
予想外だった事のうちの一つは、この噴水跡地に敷き入れられている土留めの土が存外に新しかったことだ。それでも男が手で触ったりほじくったりして確かめたところだいぶ酸化はしていた。仕方が無いので高さ一メートルほど、幅数十メートル四方のそこによじ登ると持ってきた鍬で一気に耕し始めた。初めのうちは男の奇行に皆は目だけ動かして様子を盗み見しているようだった。耕す作業だけで午前中が終わり、それから石灰や草木灰を撒き入れ、さらに丁寧に混ぜ合わせ、さらに自家製の腐葉土を入れてふかふかにした、これで土は整えられた。
男は休みなく作業した。このようなところを種々のカルテルのメンバーに見られたら…世界を良くしたいなんていう世迷いごとを深読みされて、最悪殺されるかもしれないという懸念が渦巻いて男は冷や汗をかいていた。この街には悪人か、無関心無接触の人間しか居ないんだと男は内心毒づき、汗を拭いながら作業に専念した。糞を臭わなくなるまで完全に発酵させた堆肥を肥料として穿った土に撒く、そこに、根が直接触れないようにするためにまた土を少しかけ、その土の上に植物を植えてゆく…。トラックから植物の苗が次々に運び出され、呪われた噴水跡地に敷き詰められた土の上に置かれた時、正真正銘予想外の事態が起こった。見物人たちは口々に歓声をあげ、ぞろぞろとこちらにやってきたのだった。
彼らは頑是ない子供のように目を輝かせながら植物を見ては男に訊いた…これは何て言う花なの?この球根は何だい?この種は?土は耕してあるからきっと大丈夫なはずよね?…男は面食らいながら答えていった。これはアイリスの花、こっちは水仙、この種はコスモス、土は耕したし整えてあるから育つだろう。てっきり咎められるものとばかり予想していた男は心の中で当惑した。祖母の言う通り確かに人間は植物を好む性質があるらしい…いつのまにか掃きだめと化していた広場中央の噴水跡地には人だかりが生じていた。男が作業を終えたのは夕方で、その間にやってきた警官にも質問は受けたが特段詰問されたりはしなかった。
ついに水をやり終えてから立ち去ろうとすると自分の真後ろに土色の肌の男がぬっと待ち構えているのを感じた。こいつはあのカルテルのボスだ…!!男は必死に、土色の肌の男が、自分の敵なのか味方なのかを演算していたが答えは出なかった。山岳地帯の無混血…帝政以前からの現地人特有の、灰色めいた土色の肌が夕闇に光っている。下手をしたら殺される…でも俺は街の中心がごみ溜めや死体置き場のままでいいとは全く思わない!だから花壇を作ったんだ!見返すと相手は微笑んで言葉を発した。『素晴らしい』男は彼の賞賛に暗に含まれているであろう質問を勝手に想像し、勝手に答えた。「俺は…つまり…好きでやってるんです、本当に自分ひとりで、街の広場に花が咲いてたらいいなあと俺は個人的に思って、だから…だからさ、邪魔だったら踏みつけてくれても構わないんです、だって勝手にほら…その、公の土地を、花壇にしたわけだから!」ここまで言うと男は歯を食いしばって詰問を待った、咎めを待った、死を待った。しかしボスはただ微笑んで繰り返した。『素晴らしい』…ボスが立去ると男は、その場にへたり込みそうな自分を何とか律して農地まで引き返した、この街が悪人だらけだと思っていたのは自分の勘違いだったのだろうか?
農園についてから、疲れた体に鞭打つように、日暮れ後の秘密の仕事として取引先のカルテルの車に神秘の葉を積み込みながらも男は考えていた。この葉はとんでもない濃度で凝縮され、数多の人間を溶かす、言うまでも無く俺は悪人だ。でも水に値段を付けた生活水業者は一体幾人の人間を干からびさせただろうか?俺も悪人だがそいつらほどではない、でもこの地球規模で考えると、核実験をやったり、自然破壊をする政府や企業というものの悪事は…たかが麻薬カルテルで人間同士の諍いが在ろうとなかろうと自然世界そのものには傷一つつかない、人間という種族内で完結してしまう悪と自然にまで悪影響を及ぼす悪ということと比べたら遥かに悪い、植物の売買だけを生業にしているカルテル関係者やボスよりも、自然破壊をしている奴らの方がとんでもない罪になる。そして人間が幸福であるには自分の領域から出ないことが紛争を防ぐ最大の手立てだとしたら…ああ、今日俺がやったことはやはり悪ですらあるんだ。共産党員だった叔父があの違法花壇を見たら俺をぶん殴るだろうな。でもその悪、つまり街に勝手に花壇を作った罪を誰もが喜んだ!…人間は、人間の手助け無しでも存在出来る何かを有難がるんだ。
特にそれが人間に恩恵をもたらすものであれば猶更だ、恩恵、恩寵…自然や植物はまさにこの点で宿命的に正義なのだ、人間にとっても、地球にとっても…。男は自分の中の善悪概念が混ざり合い、今までのようには安直に機能しなくなることを仕事を終えるまでずっと感じていた。「善人しか居なかったんだ」と漏らすこの孫息子に祖母は答えた。
『お前はみんなを善人にしたんだ、この街の全員が、かつて聖者様の言った通りきちんと天国へ行けるはずさ、殺されたお前の父親も母親も天国で楽しくやっているはずなんだから、いつも素晴らしい事を信じてなきゃいけないよ』
植えたばかりの苗たちに呼応してか夜半から、静かな雨が降り始めた。男は祈った、生めよ、増えよ、地に満ちよ…。祖母の言う通りなのかもしれない、その日に出会った人々は皆善人であった。苗たちは日の出前から目覚め、慈雨を思うがままに吸収し、増えて行くだろう。男は緑あふれる花壇が街の中央にあるのを想像して胸が熱くなった。地球も初めはこんな風だったのだろう…。それに引き替え自分は、己の利益だけを望む人間を悪人だと思っていたのだ、何もしない奴らを卑怯だと罵っていた…悪人はこの俺だ、誰も愛していなかったし、愛そうともしていなかったんだから。
かくして琥珀と、極彩色の夢が見られる植物の原産地であるその街の広場中央には花壇が出来上がり、季節が廻る毎に男が手入れをしたので緑あふれる憩いの場所となった。しかし男は名を聞かれても自分は一人の悪人に過ぎないとしか答えなかったため、いつしかこの花壇は敬意を表して『悪人の花壇』と呼び習わされるようになった。