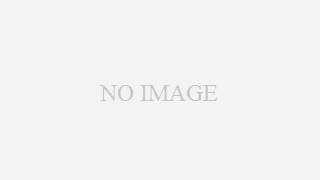骸骨の街の片隅に、今にも息絶えようとする女が自らを捨てて横たわっていた。微かな海の記憶が女に蘇っていた、初夏の匂い、青空に雲が高く渦を巻くように動いているのを見て歓喜の声をあげたことや、晴れた夜にこの海辺を、ドレスをはためかせてドライブした記憶も、まだ内部に残っていた。捨てるべきものは全てであったのに愛しいものの記憶だけは捨てることができなかったのだ。…あのまま二人でどこかへ行きたかった、そんな思いが女をこの街に留めていた。
骸骨の聖母の守護する海辺のこの街にはありとあらゆるものが捨てられていた、誰かへの想い、家族の役割、希望、素晴らしい夢、嘘、そして名前までもがこの街では至る所に捨てられているのだった。街の住人は外からくるものを羨まし気に眺めていた。この街は表向きは観光地であったがその実、すべてを捨て、どこか彼の地でよそ者となった人間たちが終の棲家に辿り着く、墓場の街、骸骨の街であった。
『片思い、それも汚れ切った年増の初恋なんて捨てるべきよ』
このような想いを抱くこの女が骸骨の街に流れ着いた当時、彼女はまだ子供で、この街に来てから自らの名前を拾った。幼い乞食であった彼女はその名前を名乗ることにはじめのうち抵抗を覚えたが、よくよく考えてみると人間個人が本当に正真正銘その名前の通りに…名づけられた時から不変の存在であるはずもなく、名前が変わろうが同じ名前を一生名乗ろうが、その人はその人であって、同時に全く、その人がその人である確証などこの世の何処にもないのだと気付いていた。だからこそ拾ったその名を…いかにも令嬢なる名を正々堂々と名乗った。過去には華美な娘が名乗っていたであろう名を、ぼろきれを纏った少女は名乗るようになった。
それからまた、その幼い乞食女はこの街を守護する骸骨の聖母に祈った…『骸骨の聖母様、白い貴婦人であるあなた、あたしはまだ子供で何も持っていません、何一つ持っていません、どうかあたしにいろいろなものを拾わせてください、あたしに必要なものを、あたしが生きていられるようにあたしを導いてください、服や食べ物を得るための仕事をあたしにください、そのために必要なものをあたしに恵んでください、あたしにすべてを拾わせてください』
骸骨の街には年齢もよく捨ててあった。この街の住人は歳をとることを拒む。彼女はこれ幸いにと10歳ほどの年齢を自分に与え、唐突に大人として振舞った…この街ではこの不可思議な現象、もとい風習を誰も咎めなかった。早速彼女は寂れた淫売宿で働き始めた。この街とはいえど金はそうそう落ちていなかったからだ。その宿の女主は女の名前を聞いて眉をあげた、この元乞食女がいっぱしの娼婦になってから女主はその耳元でこう囁いた。「それはあたしの昔の名前よ、清純で天使みたいだった頃のあたしの名前、お屋敷に住んで居た頃のね、でも家出して要らなくなったから捨てたのよ、けどここへあたしを探しにやってきたのかもね」、女はその娼館を後にし、また新しい別の名を拾ってそれを名乗った…女は知る由も無かったが、女主人は商売用のベッドに捨てられた元の名を拾い上げると数十年前から屋敷暮らしを続けていたかのように再びその名を名乗るようになり、しばらくして店を畳んで姿を消していた。
さて、女の足取りをいちいち拾っていっては大変なので抜粋すると、名前、想い、振る舞い、時に技術…そういった、この骸骨の街の住人にしか見えない何かを拾ってさえいればどうにかこうにか暮らすことが可能だった。ある日、庭、が街路樹のそばに捨てられているのを女は見て取り、その庭を拾い、自らのものにするとさっそくその庭の実際にある場所へ出かけ、その所有者として工事にかかった。といっても大工を呼ぶ金は落ちていなかったので女はかつての娼館で稼いだなけなしの金をはたいてレンガを買うと庭に小道を作り、庭がそれらしくなってくるといよいよ嬉しさは募った。ほどなくして女は自らをそこの女主人と称し、さらに薔薇を植えて優雅に暮らすようになった。
薔薇の香る庭の女主人となってから女は観光客たちを呼んで連日連夜パーティーをした。彼らが捨てるものには地位や名誉、重圧のある伝統などさえも含まれていた。骸骨の街の住人である女にはそのすべてが文字通り手に取るようにわかり、直感的にそれらを拾い上げて自分自身の装飾品にした。祭りの日々は続き、女はますます輝き、客たちが捨ててゆくすべてを拾ううち…元乞食の女はいつしか裕福な夫人の一人になっていた。
人間が捨てるものの中には、伝統やしがらみと一緒に裕福さや気品といったものが含まれているという事実に少なからず女は驚いていた。気品というものを軟弱と見なす一部の人が捨ててゆくので、それをまた、女は物腰も柔らかに拾うのだった。自分の出生を考えたら到底手の届かないような人間世界に自分が居るのを、元乞食の今や貴婦人ですらあるこの女はくすぐったく思った。その場所でまるで女優のように優雅に振舞うのをどこかで傍観しながらも女は思った。『でも幸せは捨てられていないのね』
骸骨の街を守護するのは骸骨の聖母だった…『聖母様、あたくし色んなものを手に入れましたけれど、まだ幸福は手に入れていませんの、恋はよく捨てられているけれど本物の情熱を捨てる人は居ないわ、清らかさを捨てる人は案外いるけれど、死んでもいいという情熱を捨てる人は一人も居ないの』骸骨の聖母は女の話を聞きながら微笑んでいた。まるで破滅の恋を教えようとする街はずれの呪術師の老婆のようであった。
『本当にめちゃくちゃになってしまいたいのよ、この人がすべてとお互いに思い合うような恋がしたいの』…しかしそんなものは落ちてはいなかった。そういったものは人が、たとえ骸骨と化してもその手に掴んで離さない類のものだったからだ。その代わり、秋の夕暮れ、観光客たちが北へ帰っていった涼しい海辺の近く、とある橋のたもとにそれは落ちていた…この街の住人にはほのかに光るその淡い球体が何であるかはっきりとわかった…女が拾ったそれは初恋だったのである。
夕日が沈み切って潮風に夜が含まれるころ、橋の街灯にはオレンジ色の明かりがぽつりぽつりとともった。そこを一人の男が歩いてくるのが見え、女はわけもわからずそれを見つめていた。声をかけることなど出来ようはずもなかった、恥じらうということがどういった事なのかこの元娼婦の女はすぐさま理解し、おののきながら薔薇の庭の邸宅へといそいそと引き返した。
唐突に始まった初恋感情に女は戸惑っていた。『あの人はこの街の住人なのだろうか?あの人もまた、この街に捨てられたいろんなもの…名前や年齢や社会的地位、そういったものを拾い集めて生計を立てているのかしら?いいえあの人に限ってそんなはずはないわ!あの人は…あんなに素晴らしいんだもの!!…話した事も無いけれどそれはわかるわ』途端に周りのすべては灰色になり、女には、その男だけが虹色に輝いて見えるようになった。
果たして男と女がどちらからどのように声をかけたのかはわからない、二人はほどなくして誰も居ない秋の浜辺でもつれ合う仲に至っていた。傍目に見ればそれはどこにでもありふれた男女の出会いの一つに過ぎなかった…しかもそれが女からの思い込みの恋であることすらも見て取れた。男は、この美しい女を横目にいつも遠くを見ていて、生理学的な事情、一種の刺激による反応といった理屈で女と寝ころぶこともあったがそのほとんどの時間を独自の考えに従って行動している様子だった…つまり彼はこの街の住人ではなかったのである。
女は自分で組み立て挙げた演劇に夢中になっているのを心の中ではわかっていたがそれでも情熱に身を焦がす喜びに浸り切り、男に語りかけていた。『風のなかにも海の潮騒にもあなたが含まれてるってことを考えてるのよ、いつも気持ちはあなたへ向かうの、何をしていてもどんな時でも、(いろんな人と恋をしたしいろんな人と寝たけど…と言いかけて女はこの件について伏せた、正直が美学でないことくらい、あの淫売宿でとっくに学んでいたのだ)、あなたの事を考えると胸がしめつけられるの、ねえ、夏が好きなあなた、夏の来る前のあの初夏の香りをいっぱい楽しみましょ、夏が来たら青空に入道雲を見て二人で乾杯するの、晴れた夜にはこの海辺をドライブしましょ、車はまだないけどすぐに手に入れてあげる、ああもうそこに居るみたいよ、あなたと二人で、今年の夏はまだあたしたち出会えなかったけれど、今こうして秋の潮風に吹かれてるともう、今言った景色の場所にあたしたち居る、そんな気分になるのよ、もう辿り着くべき場所へ辿り着いたっていう風にね』
女が話し終える前に男はおもむろに姿勢を変えた。女を抱き終えたばかりの男はこの状態特有の青ざめた顔をして海の果てを見つめて呟いた。それは小さな水生生物の呼吸のようでもあった。「南へ行かなきゃいけないんだ」他の観光客が北へ引き返したのとは違う行動を選択しているということが、今まさにその命を終えようとしているこの淡い初恋を握りしめる女にとって唯一の慰めであった。この人は特別な人だから南へ行くんだわ、いつまでも夏に居たいからそうすべきなのよ…女は言った『私もついて行っていい?』
明日の朝、出立すると男は言った。男は女が歳を食っていることを傷つけないようやんわりと伝えた。「君は長年過ごした場所に残ったほうがいい、君には落ち着いた生活が必要だろうから…」その言葉がかえって女を湧き立たせた、女は半ば半狂乱になって言い返した。街灯がきれいに化粧した妙に美しいこの女の顔を赤く照らしているのを男は観ていた。
『あたしすべて捨てます!要らないのよ何も、あなたにはわからないかもしれないけれどこれっぽっちも本当に自分自身だって言えるものなんか持ってないのよ、持ったこともないのよ、全部が全部、人から…その…譲り受けたものなの、あの土地も、この海辺の夫人だという地位も、だってあたしが一体誰の夫人だっていうの?拾ったものは捨てていくわ、ええ、ここにね、あたしここの生まれでもなんでもないのよ、他の街から逃げてきただけなのよ幼い時にね、それで全部拾ったの、名前も全部、あたしが年増だっていうなら年齢も捨ててくわ、本当より10歳も年を食ってるんだから!もとはといえば働くために年増になったのよ!全部全部捨ててゆくわ!』
秋の夜更けの浜辺で、波音を聞きながら余所者に過ぎない男は女の言う言葉の意味を、理解しかねるといった風にどこか遠くから見つめて黙っていた。女は意を決した風に突然さっと立ち上がり、服の裾を持ち上げ、瀟洒な靴を意にも介さず砂を蹴って勢いよく走りだした。振り返りながら彼女は叫んだ。『明日の朝、朝日が昇るころに橋のたもとで落ち合いましょう、どうかあたしを連れて行って!』
男はややあっけにとられながらも頷いた。もともと気ままな旅であったし、女は何不自由なく暮らしている風でもあるのでそこまでのお荷物にはなるまい、ひょっとすると生活を工面してくれるかもしれない、いい加減我慢できなくなったらどこかに捨てていくのも手だ、そんな打算もあり男は明日の朝には顔を見せようと決め、さっさと宿へ戻って眠りについた。
女にとってはそれからが一仕事だった。この街の住人がこの街を後にするならば、この街で拾った一切のものは捨ててゆくこと…それが骸骨の聖母と、それに守られる住人との間に交わされている契約、もとい、信仰だった。…ここで示される信仰とは真実という意味を含んでいる。ともかく彼らには事実それが可能であったのだ。名前や年齢や地位を拾い上げることも、初恋を手にすることも、恋を捨てることも、すべてを捨てることも。
女は靴のかかとが擦り切れるのも構わずに真夜中の海辺の街をひたすらに走った。『骸骨の聖母様、骸骨の聖母様、白い貴婦人、どうかあたしの祈りを聞き届けて下さい、あたしすべてを捨てます!この街を出てゆきます!』女は胸元からひとつひとつの光の球を取り出し、その一つ一つを順番に捨てていった。…気高き夫人の気品を、浜辺のテラスにひとつ、見たこともないたくさんの威厳ある親類を、街灯の下にひとつ、またひとつと転がしておいた。人をもてなす術や、明るい笑顔の作り方も、女としての完璧な振る舞いも、女はひとつずつ潮風の路地に捨てた。一番きれいに見える化粧のやり方やたくさんのドレスも同じように捨てていった。女の住む薔薇の庭の邸宅では女がこの街で拾ったものが捨てられるたびに、それと符合するものが魂を失っていった。数えきれないほどのドレスにはすでに100年分の埃が積もり、化粧台は朽ちていた。女が捨てるのを拒んだ最初のものは薔薇の庭であった、あの植物たちの安らかな庭を捨てるのはさすがに気が引けたが、何かが女を促し、女は自分自身から薔薇の庭の光を街路樹のそばに捨てた…その途端に薔薇は散り庭の草木は枯れ果てた。すでにそれを捨ててしまった女には最早知る由もないことであったが。
女がほとんどのものを捨ててしまったとき…今の名前や、娼館での通称、初めて拾った名前はもう捨てていたのでそれについては思い出しもしなかったがようやく、かの寂れた淫売宿の女主がなぜ自らの名前を捨てたのか少しだけ理解し始めていた。女は思った。『どんなに大事なものでも…捨てなければならない時ってあるんだわ、自分が幸福になるためにはすべて捨てなければならない時っていうのが、人生にはあるんだわ…』そして女は10歳分の歳を捨てた。しかし女は若返るどころかすっかり肉が削げ落ち、痩せこけて、昨日からそのままの化粧はまるで死に化粧のように見えるという形相だった。女はあまりにもこの街に馴染み過ぎていたのだ、女はあまりにもこの街によって形成されていたがために、人生のほとんどを捨てた女はすっかり自身がすり減ってしまっていたのだった…朝焼けが骸骨の街に迫っていた。
『あと、ひとつだけ…』しかしこの街で拾ったもののうち最後の一つというのが、件の初恋、であったということはなんという皮肉だろう。女は未だそれを胸から引き出せずにいた。海辺の空は赤く染まり始め、女の目の前には骸骨の聖母が光輝きながら現れて虚ろな眼窩で女を見つめて笑っているのだった。すでに橋のたもとまで来ていた女は裸足の足をこすり合わせながら声も無く泣いていた。
美しい挙措を失った女は秋の朝の意外な寒さに打たれたまま、涙の流れるままに、現れた骸骨の聖母を見つめ返した。優雅な貴婦人から一夜にして変貌したその姿、立ち振る舞いはまさに物乞いのそれであった。ぼろ雑巾のような女は言った。『ねえ、骸骨の聖母様、あたしすべてを捨てました、でもどうかこのひとつだけは見逃してください、この拾い物をあたし自身だと言わせてください、お願い、骸骨の聖母様、あたしあなたに何でもするわ、これをとられたらあたしはあたしでなくなってしまう、だってあたしには本当に何一つ無いのよ、何も持ってないの、はじめっからあたしである部分なんてどこにも無かったのよ!!あたしがあたしであると宣言できるものなんかこれっぽっちも無かったの!お願い、最後の一つは見逃して頂戴…』
骸骨の聖母はいかにも優し気に微笑んでいた。すっかり乞食となった女は続けて言った。『あたしが今生きてるって感じられるこのことも、もしかするとこの初恋のためかもしれないの、だってこの初恋を知らなかったあの時はいくら贅沢な暮らしをしても満たされなかったもの!わかってる、わかってる、あなたの言いたいこと、片思い、それも汚れ切った年増の初恋なんて捨てるべきよ…そうでしょ?』
女の涙が痩せ衰えた肌をつたい、粉を吹いている化粧をさらに醜く流していった。女は続けた。『…ねえ、この初恋を捨てればいいんでしょう?そしてまた今しがたあたしが捨てたものたちを拾っていけばいいんでしょ、そうでしょ?そしてまたあたしは薔薇の庭の邸宅の、気品に満ちた優雅な夫人に戻るの、ええ、白い貴婦人、骸骨の聖母様、あなたの言うとおりにすべきよ…だけど出来ないの!あの人と嗅いだ初夏の匂い、あの人と見た入道雲、あの人とドライブした海辺の街の…ええあたし本当にそこに辿り着いていたのよ、行った事のない場所ややったことのない思い出を捨てられないの!あたしがいちばん、自分が自分だと思えたことだから!』
朝焼けがくっきりと女の顔を照らした。女は街から出ようともがいたまま、それでも胸に手をあてて、まるで心臓を取り出されるのを拒むような格好で橋のたもとに倒れ込んだ。その場所で女と骸骨の聖母との間に、果たしてどのようなやりとりが成されたのかは誰にもわからない。
しばらくたって軽い朝食を済ませた件の男がやってきたが…美しい夫人の姿が見当たらないのでしきりにあたりを探していた。とその時、橋のたもとに大きなゴミのようなものが横たわっているのが見え、反射的に男が近寄ってみると、最早皮と骨だけになった女がぼろきれを纏った姿で息を引き取っているのだった。男は何処の誰ともつかぬ死体を見た驚きに悲鳴をあげてその場を一目散に逃げ出した。しかもその死骸はまるで10年もそこに放置されていた様子で、死に顔はまさに、骸骨の聖母のようなのであった…。