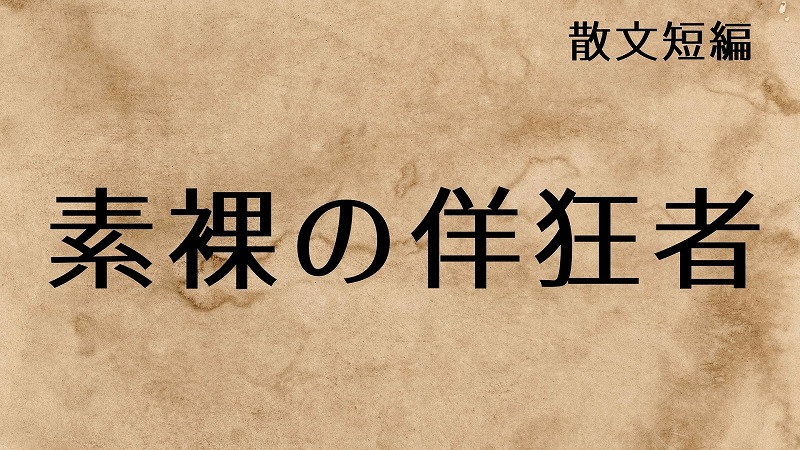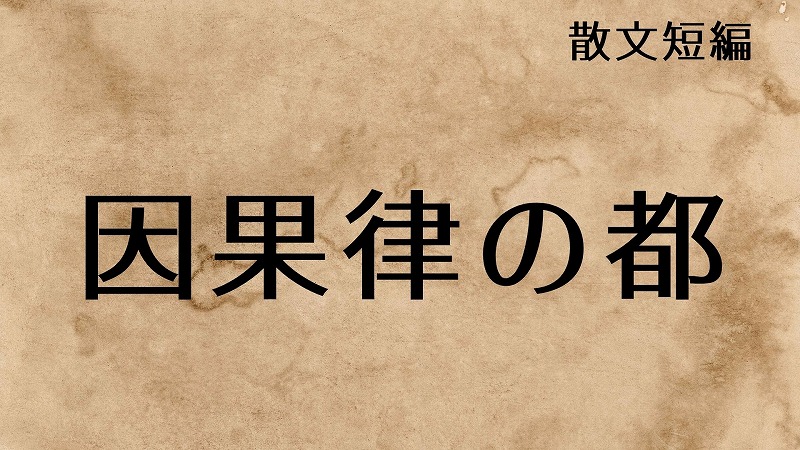神の子が地上で磔刑に処されてから幾百年、牧草地を横切り、荒野を彷徨い歩きながら素裸の佯狂者の男は両手を世界へ向けて広げた。全ては神の恩寵に包まれていた。人間世界はその中に在って実に閉鎖的に機能している。雪の降る中でもこの男は裸であったし酷暑でもそこいらを歩き回っては神の恩寵を人々に告げ知らせていた。毒のある植物かそうでないかは神に訊ねるよりも先に恩寵の中に在れば自然とわかる事であったので、彼は草を食み、虫を食み、自身が草草やあまたの虫で構成されるのを市街地まで赴いては面白おかしく眺めていた。この世に一つの余りも残さずに完結できることを心から喜んでいた。この素裸の男は稀に怒りだして人を問いただすこともあった…だが一般的な悪事を働いているであろう人々を彼は叱責しなかった。
高利貸と仲良く飲食し、取税人と朗らかに語り、酔って娼婦と歌い、密通している仲の二人に神の祝福を与えさえもした…その代わりにやけに白いパンを売る商人を怒鳴って石灰入りであったことを認めさせ、子供に猥雑な事をさせる高僧に唐突に殴りかかり、中毒になっている酒飲みから酒瓶をひったくって代わりに自らしこたま飲んだ。その様子は傍目には、パン屋にいちゃもんをつけ、市民に慕われる僧侶に殴りかかり、酒飲みから酒を奪って自らの肌寒さを和らげるがためにそれを飲み干すというとんでもない素っ裸の蛮人に映った。
こういった理由から人々の目には全く賞賛に値しない素裸の世捨て人というのが彼の評判であった。この男が神について、また世界の恩寵について絶えず口ずさんだり時に胸が詰まったように黙したりしながら野を彷徨うのを遠目に見つつも、近寄ってきたら石を投げる者さえあった。彼の唯一のわかりやすい長所と言えばこのような事態に直面してもしかめっ面ひとつせずにキリストの磔刑についての祈りをあげ、相手を慈しむ眼差しを向けることであった。
…ある時この素裸の男は王に呼ばれた。王は言った。『貴君は聖者だと言うがそれは本当か』男は王に対して放屁しただけで何も答えなかった。程なくして城からつまみ出された男は心の内で呟いた。どうして聖なるものとそうでないものを敢えて作り出すのだろう?もし自分が聖なるものであるならばまさにこれがために罪びとが生じるというのに…人間は人間の囲いの中で生きている時には除外されのけ者にされ選ばれないものになるのを酷く厭う、これを避けるためだけにさえ戦まで起こるというのに。
…また別の領主からも男は呼ばれた。領主は言った。『私の専属聖者として常に味方になってほしい』男はげっぷをするとその場を立ち去ろうとした。領主はまた言った。『何でもやろう、毛皮でも靴でも金でも』男は裸足のまま、来た時と同じ素裸の恰好でその邸宅を後にした。意外にも男は毛皮が暖かいことも靴を履くと足が痛まない事も知っていた。でも金を使って守ってやりたい味方は一人も居なかった。味方を作れば敵が出来てしまう。靴を履けば二度と脱げなくなる。毛皮を着たら心持では生皮とくっついてしまって、それを引きはがされる時には信じがたい苦痛を味わう羽目になるのを男は知っていた。何のためにもならないことをやるのが恩寵に近づく手段である。利己心から来る恥を全て脱ぎ捨てることが神に対しての従順を示す最短の手段である…。
街中を、荒野を行く羊のような足取りで歩き、絶えず生贄として屠られるために人目をはばからず主を賛美する人間を佯狂者と言う。牧草地を横切るときに親切な人が近寄ってきて暖かい乳の入った椀を差し出す。男は神の祝福を相手に与えてからそれを飲み干す。本当はこの世に聖でないものは何もない。誰もが聖者なのだ。しかし何かのために行動するのが人間の軸となったがために、自分は狂ったものと見なされる…それでいい、それでいい…素裸の佯狂者は両手を、自分と世界へ向けて広げた。人間社会を含め全ては最初から最後まで神の恩寵に包まれているのだった。