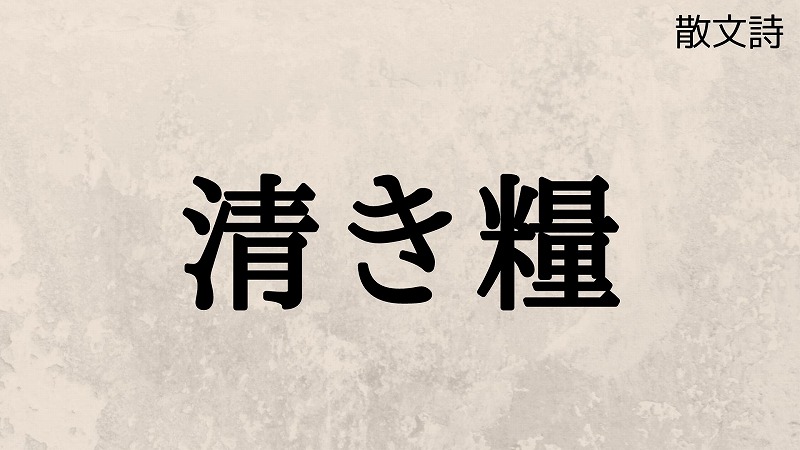焚火が森の人々を照らしている、夜は人の世界ではなくヌイの世界だ。盲目の声聞きの老婆は耳飾りと首の玉飾りに時折触れながら森を生きる同胞への叙事詩を語り聞かせていた。麻で編んだ服、肌には油を塗って寒さを防いでいるこの人々は石や弓を使って狩りをし、昼は木の実を拾って移動しながら生活している、モ(たくさんの)リ(木)の人と彼らは自分たちを自称した。明白な血族関係は母子以外には無く、その代わりに男たちは狩猟のやり方や幕屋を器用に作り、その技能を子供らに教えていた…教えることの上手い男を子供らは父と呼び、そういう男は女にたいそうもてたので、自然に男たちは率先して技能を身に着けるようになっていた…。冬が近づくと南方に移り、春になると夏に備えて北上し、沢山の保存食を担ぎながら常に歩く、それが彼らの『太古からの』生活だった。名前の付く以前の歴史を生きた人々の暮らしを『森の声聞き』と呼ばれる役目の、盲目の老婆は語り、この役目に就いたものは集団の次の移動先を決める習わしだった。その時、その場には居らず、皆からかなり離れた場所に設置された幕屋に横たわる女が叫び声をあげた、産気づいたのだ。
生まれたのは女の子だった、声聞きの老婆は指で余すところなく嬰児を調べ、その頭と体にさしたる障りはないとわかると森の霊であるヌイの声を聴いて祝福を与えた。それからまたはっとして女の嬰児の脚の付け根をしつこく触れたが、老婆は思い直したように黙っていた、皆固唾を飲んでその様子を見守っていた…こうして一人の女が誕生した。だが誰にも名前は無かった、彼らは誰であっても彼等であったし我らと言うその一人称こそが固有名詞でもあった彼らに個人名は不必要であった。そして常にまとまって暮らしていたので取り立て誰が誰である必要は無かった。誰が誰であっても良かった…声聞きを除いては。
女は帯紐を昼は腰に巻いておき、夜になると帯紐をたたんで枕にし、その枕を持って何処へでも『その時に』好きな男のところへ行って寝た。婚姻関係というものは無かったし、全員が全員とも家族であり、女たちの好む通りにさせておけば生命の摂理で必然的に血の遠い者同士が結ばれた。枕を寄せられることは男にとっての栄誉でもあったがその効力はたった一晩に過ぎなかったので大抵は固執することもなかった。男も女も長い髪を編んで魔よけにし、殊に男は狩りの都合で幕屋の外で眠る事もままあったので女よりも長い髪を束ねて枕代わりにしていた。麻の服には模様が描かれており、それらは冷たい風から、森の獣の牙から、身体の腐る病気から、ありとあらゆる忌むべきものからの魔よけであった。女たちは稀に手が空くと染め具で模様を描いては好いた男にあげた。それでもこの集団で誰からも魔よけをもらわない人間は無かった…そのあたりの采配も声聞きの役割であったし、第一に貞操概念といった善悪の存在しない女たちは制限なく魔除けを作っては、純粋な親切心から仲間たち皆に配っていたからだ。しかし漠然と魔よりももっと大きな何かが果てしないほどの森全体を覆うのを声聞きの老婆は感じていた…悪霊でもヌイでもない、それは紛れもなく沢山の人間の眼であった…。
霊たちは絶えずあたりを行き来して声聞きに様々の事象を知らせていた。でも大抵は置いて行かれたものであり、中にはわざと間違った情報を伝えてくるものもあったので声聞きの老婆はその中のどれを選択するかを絶えず逡巡していた。その取捨選択こそが声聞きの仕事であった。霊は皆影を縫い付けたように付きまとうのでヌイと呼ばれていた。
『あれはいいヌイだ』『あれは悪いヌイだ』そんな風に声聞きは言って森と一体化した霊魂、すなわちヌイの声を聴く。川の傍に春まで居るかどうか、魚にありつけるかどうかよりも雪解け時の思わぬ氾濫を避けた方が無難か…。一行は増えたり減ったりしながら絶えず旅を続け、旅を続けるのに支障のあるものはその都度置いて行かれ幾年かが過ぎた…5年、10年、世代は変わり、いつしかかつて生まれた女の子も子を産めるほどに成長していた。だが彼女は一行の中に相手を見つけずに夜に幕屋を抜け出しては翡翠色の水辺に行き、そこで何者かを待っているのだった。少女は影を待っていた、彼女の目には麗しい男の亡霊が映り、男の亡霊はつまるところどこかの時代に頓死した若者に過ぎなかった…この時空間が果たして過去を示すのか未来を示すのかはたまた別の時空間を示すのかは互いにわからなかったが、ともかく亡霊が来ると少女は服をはだけさせ、影のような相手を自らの身体に迎え入れ、悦びの声をあげるのだった…。
『ヌイと交わるんじゃない!』ある時声聞きの老婆は叱って少女と霊の逢瀬を引き裂いた。しかし少女の腹は膨れ始め、季節がいくつか過ぎ去る頃に産気づいた。
生まれたのは透明な液体のような子供だった、それを子供と呼ぶにはあまりにもおぞましいので産婆も声聞きの老婆も凍り付いたようになって口をきくこともしばらく出来ないほどであった。言うまでもなくその子供は夜が明けぬうちに早々に葬られ、土をかぶせられた。少女は出産を経たので成人したと見なされたが祝される事は無く、次の移動先を見つけるまで…季節が変わるまで呪いが皆に広まらないよう一つの幕屋に閉じ込められていた。この珍出産の祟りなのか、『女』となった少女は清めの期間を過ぎて次の場所へ移動することになった時に足の付け根に痛みが走り、うまく歩けなくなっていた。
『ヌイと交わってたくらいなんだからお前、ヌイが見えるんだろう?』声聞きの老婆の問いに女は頷き、今も来ていると呟いた。『何人来ている?』女はあたりを見回してはっとした、自分の両目を誰かが覆っている、それは目の前の盲目の老婆ではなく明らかにヌイの手であった。幕屋の周り中をヌイたちが取り囲んでいるのが解る、ほんの隙間にさえも様々の目が光った、そしてそのどれもが置いて行かれたものであることを女は理解してわなないた。こんなにたくさん!!女は指を突き出して叫んだ、指の数よりもたくさん、いいえひょっとすると髪の毛ほども居るかもしれない、数えきれないくらい沢山のヌイ!!!『この中のどれがいいヌイかわかるかい』女は泣いていた。『答えられないとあんたは置いて行かれるんだよ、一人では歩けないような者をわざわざ抱きかかえて連れていけるわけがないじゃないか!答えられたならお前を次の声聞きにする、声聞きになればお前は置いて行かれずに済む、次に産む子が玉のような創一つない子ならお前だって立派な母親として祝福されるんだ、さあ答えなさい、この中のどれがいいヌイかわかるかい?』女は死者の霊に目隠しされてそもそも見えていないその視界をさらに閉じるべく両瞼を閉じた、涙はとめどなく溢れている、自分の母親さえも心配して幕屋を見守って祈っているのを感じていた。さらに瞼の奥の…肉体的に光を感じる部分、その瞼さえをも女は閉じた。こうして三重に瞳が閉じられたその時、自分にぴったりとくっついて抱擁するかのようにすべての…悪霊たちからの視線を防いでくれているヌイの居ることを感じ、それを声聞きの老婆に伝えた。
かくして翌日から女は新しい声聞きとなり、代わりに盲目の老婆の声聞きはその地に置いて行かれた。
この呪われた出産によって歩行困難に陥っていた女は普段木の杖を使ったが、移動の時にはほとんどの歩行を集団の誰かに手助けしてもらいながら進んだ。それは少数気鋭が基本の彼らにとってはかなり手間のかかる事ではあったが、そもそも、次に何処へ行くべきかすら声聞きである彼女が指示しなければ一行は一歩も動けなかったので、声聞きを助けることは彼ら自身を助けることに直結していた。それほどに森の持つ魔力は強大で、ヌイたちは得体の知れぬ…カミとも魔ともつかぬ森の亡霊たちであり、こういった謎そのものに囲まれての生活に於いて、謎と対峙出来る声聞きは重要な存在であり、小さな灯でしかない生きた人間は、どんなに強靭な肉体を持とうとも脆弱な存在でしかないというのが彼等モリの人の基本的概念であった。自分たちの身体と森とは母と子のように臍の緒、つまり魂の紐で結ばれているものの、森をはじめとするさまざまの自然現象の前に人間など無力であることを彼らは自覚していた…このような理由から声聞きの場合は身体に『障り』があっても移動に於いては助けられたが、声聞きとなった彼女を助けるのはいつも一行の余り者と決まってはいた。
余り者というのは特段技能もなく、暗に女から想われていない男を指した…出産でたびたび命を落とす女は集団の中で絶対数が少なく、一方で常に男は余っていた。性の不供給、これはいわば彼らにとってのタブーであった。そんな中での女同士の諍いを避けるために声聞きの役割に就いた女は人気の男には近づかず、他の者に世話をさせるという措置がとられていたのだ。声聞きの女は余り者の補助者の為に率先して魔除け服を作ってはそれを着させ、時に彼らの無作為な髪を自ら編んだ、とはいっても声聞きとて肌を合わせるのは好いた男だけだったので彼らはこの種の親切に対してもいつもどこか恨めしそうにしていた。この均衡を破るのを恐れてか女は夜になると幕屋を抜け出て、この集団の中で情をやりとりすることを徹底的に避けた。気が付くといつか若者の亡霊と交わっていたあの渓谷に来ていた、水は澄んで夜だと言うのに翡翠の羽の色をしていた。女は、結局いつまでも自分が群れの中で一人きりであるように感じ、そこでさめざめと泣いていた…その時だった、すぐ近くで笛の音が聞こえた。
ヌイか?あるいは森に溶け損ねた悪霊か?しかしそこには見たことのない顔立ちの生身の男が立っているきりであった。
その男の着ているものは模様の無い服で髪は簡易に束ねられているだけだった。ほどなく男と女とは恋に落ちた。夜になると声聞きの女は寝床を抜け出し、足を引きずりながらも逢瀬のために忍び出た。男は女に名前を聞いたが女は意図するところがつかめずに漫然として笑っていた。
『私たちは私たちよ』そして肌を寄せ同じ言葉を繰り返すのだった『今だって私たちは私たちよ』交わりながらも『ほらね、私はあなたであなたは今私でしょう』皆が起き出す前に女は帰っていった。しかし内心魔除けの無い服を着て真っ暗な森を出歩く男の事を訝しんでも居た。彼は森の力を微塵も感じないのだろうか?ある晩、女の身に着けている文様を男は笑いながら撫でた…その時、瞬時に守りの光が消えてゆくのを女はまざまざと見て男に尋ねた。『何故こんなことをするの?』男は、自分たちの住んで居るところでは魔除けは必要なく、代わりに必要なのはこれだと言って光る細長い何かを女に手渡した。それが剣というもので、人を殺すものだと男から教わったその時に女は悟った…魔よりももっと厄介なもの、かつての声聞きの老婆がたまに口にしていた忌むべきものの名を聴いたことを悟った。男は自らを『空と海から渡って来たカミの子』と称した、女はそれとなく男の住む集団の位置や移動速度を聞き出して口づけをした。口の中に噛んでいた毒草の働きによって恋しいが厭わしい恐るべき男はあっけなく死んだ。女は男の短剣を密かに抜き取ると皆の所へ帰り、翌朝すぐに群れを出立させた。
ぐずぐずしている暇は無かった、凄まじい速度で北へ逃げなければ自分たちはおそらくカミの子らに皆殺しにされる。…海から渡って来た猛者共に森という存在が解体されていると女ははっきりと理解していた…女はこの点に於いて一人の人間ではなかった、声聞きとはそういうもので、自分ひとりという単位で物事を考えてはおらず、モリの人である自分たちすべてに取り付けられた目玉であり耳であり口なのであった。声聞きの瞳として森を、海の向こうを見て身震いしていた、『古来』のようにはいかなくなる…。
魚の獲れる温暖な浜辺は既にカミの子たちが占拠し始めていた。季節は廻り、声聞きの女はかの男との間に孕んだ子を産み落とすと躊躇なく剣で刺し殺した。この様子を見たたったひとりの産婆のみが呆気にとられていたが、なにせ声聞きのすることなので意図があるのだろうと察してか何も言わず、黙ったまま鉄の剣だけをじっと見つめていた。人を殺すためだけの道具をはじめて目にしたであろうその産婆は明らかに動揺していたが声聞きは剣を見たことを誰にも言わないよう言い含めた。…強力な呪力を持つとされる声聞きの命令を、無論、産婆は黙って受け入れた。
広大な森の中でたまにすれ違う別のモリの人の集団と話し合い、カミの子たちが海辺に『ささって』いることを互いに漏らした。カミの子らはどうやら春夏秋冬の一年中を同じ海辺にささったまま過ごすらしい。カミの子らに森の人が捕まると女は決められた男にあてがわれ、枕を変えることも女の意志で寄せることも叶わず泣きながら暮らし、モリの人の男がカミの子らに捕まると即座に殺されるらしい…。こういった事情からモリの人らの集団はかえって一か所にまとまると危険であると察知し、今まで通り分散し、魚を諦めてより一層森の奥深くへと足を運んで北の地へと進むより他無かった。次第に生活は苦しくなり、魚や貝の不足からか赤ん坊はすぐ死んだ。一行はだんだん声聞きの女に対して不満を持つようになった。
ついに事は起こった、一行の中でいつもどの女も寄り付かずにいた余り者の男がカミの子らと通じ、モリの人である自分たちの集団の女をカミの子らに受け渡すと願い出ていたのだ。自分もカミの子の所で言いつけを守って働く代わりに自分にも女を誰でもいいから一人あてがってほしい…このような取引が行われていたのだ。
これを見抜けなかった声聞きの女は大いに自分を恥じた。どのヌイも何も告げに来なかったのだ…おそらくこの剣を傍に置いていたのでモリの人の霊魂であるヌイ達は声聞きに近寄ることが出来ずに居たのだと周囲をカミの子の剣に囲まれてようやく気付いたのだった。翡翠色の渓谷の傍に張られた森の人の幕屋の周りを、あの時…声聞きになったあの日に見たヌイのと同じくらい多くのカミの子が、剣と呼ばれる煌めく道具をこちらに向け、まるで獲物でも射るかのようにぐるりと四方を取り囲み、焚火に照らされているのだった。たくさんのたくさんのカミの子、数えきれないくらいたくさんのカミの子!!!
声聞きの女は最早どのような魔除けの模様もどのような呪詛も通じないことを心から嘆いた。モリの人の女が枕を腰に巻いているのはそこを通じて新しい魂が生まれるためで、決して女に交わりを無理強いしてはならないというモリの人の古来からの掟が今、完全に打ち砕かれようとしていた…それだけは避けねばならない…魂を汚す行為だけは避けねばならない、穢れとは命の不自由さだけに宿るのだ。
声聞きとしての使命が女に信じられないほどの力を与え、やらなければならない事を促した。殺人を促した。四肢には力が入らなかったが剣は密かに持っていた。カミの子らはモリの人に、殺人や強奪という概念が欠如していることを知ってか実に打ち砕けた様子で談笑し、モリの人の女たちの両手を縛って朝になったら連れて帰ろうと、あろうことか酒を飲んで焚火の灯りの傍に寝転んでしまっていた。夜は更けていった。…声聞きの女も足弱と軽く見られていたので誰も注意を払わなかった。声聞きの女は密かに音もなく這い、自らの嬰児を殺したのと同じやり方で…その実、善きヌイの囁く獣殺しの方法通り、静かに同胞の心臓を一突きして尊厳の死を実行した。モリの人は、毒草と置いて行かれる以外の殺され方を件の産婆以外誰も知らなかったので、死ぬ間際まで声聞きが何故光る刃物を胸という部位に押し当てて来るのかを理解していない様子であった。超自然の力としか言いようのない胆力で幾人もの心臓を突いて回り終え、血だらけになった剣を手にしたまま、呪われた声聞きの女は森の奥深くへ消えた。しかし声聞きの任務、霊魂…ヌイたちを導くという声聞きとしてのやるべきことはまだ残されていたのだった。翌朝、残っていたモリの人の男たちは…通じていた当人も含め、女たちが一人残らず殺されている事態に憤慨したカミの子らの手によって同じように一人残らず惨殺された。
こうして実質、この集団は絶えた。
しかし呪われた声聞きの女は昨夜殺して回った女子供といった同胞たち、および今朝方殺された男たちすべての、仲間であるモリの人のヌイを引き連れてカミの子の領域から逃げていた。生者はこの女以外誰も居なかったが尚も団体は存続していた。もっともこの内情を知るものは誰も居らず、別の集団のモリの人…その中でも霊感のある者が彼女を見ても、気の狂った一人の声聞き女が霊魂と共にひたすら逃れ、ひたすら謝りながら森林の内部を巡回するのをただただ気の毒に思うだけであった。この時期にいくつものモリの人の大集団がカミの子らに捕まり、多くの場合、半ば強引にカミの人らの集団に引き入れられ隷属させられ血は混ざり、モリの人の血は薄まった。最早モリの人の見出す神秘は消え、迷い嘆く森の人のヌイの声だけが悪霊としてうっそうと茂る原生林の内部に木霊しているのだった…。声聞きの女は自らの失態をひたすら悔やんだが剣は手放さなかった、それほどに人間が恐ろしくなってしまったのだった。
女は長い間、はた目には一人で森をさまよい、悔やみ続けていた。あの時カミの子の男となぞ交わらなければ…あの時ヌイと交わらなければ…誰も傷つかずに逃れることが出来たであろう神秘の道順を思い浮かべては亡き仲間のヌイ…亡霊たちに語りかけていた。観測不可能とされる霊魂と生者との領域に於いても物語は続いていた。…多少滑稽な事ではあったが、死後の時点、あるいは『死後の地点』に至って初めて声聞きの女の霊力を『信じた』ヌイもあった。死後本当に観測し続けられる事実を目の当たりにしてヌイの姿で生前の非礼を詫びたものもあった一方、怒り出す者も居た。これだけヌイが見えていたのだから助かる道しるべをどうして気付けなかったのかと絶え間なく声聞きを叱責する霊も居た。そのようなヌイに声聞きは常に謝り通していたが、ある時問うた。
『じゃあ私たちのうちで…初めて人間を根源的に恐れた人間の中で、剣を手放せたものが居るだろうか?これからも剣を手放せる人間が居るだろうか?カミの子らも人間が人間をたくさん殺せると知ったから怖くて剣を手放せないのだ、私たちもそうだ、私たちの誰もがカミの、小さな子どもになっていつまでも母を求め、恐ろしい恐ろしいと言って泣くカミの子になってしまうだろう、いずれモリの人は一人も居なくなってしまうだろう、怖いから怖いものに先んじてなってしまうことから逃れられる人間は何処にも居ない、ヌイの微細な囁きに耳を澄ませるよりも殺されないために気を張る事を選んでしまったこの声聞きを、恨むがいい、恨むがいい、霊魂の尽きるまで恨み切るがいい』
殺されたヌイたちはこの時空間に換算するとおおよそ数年間声聞きにつきまとっていたが、一人また一人と自身の霊的末期を悟り、いつの間にか全て、深い森の中に『置いて行かれ』ていた。季節は幾度も幾度も廻り女の髪は雪解けの土のような白髪になり、時節はちょうど春になりかけていた。
呪われ、年老いた声聞きの女は小さな草の芽を撫でてから観念したように剣を静かに地面に突き刺すとぽつりと呟いた。モリの人はもう居なくなった。何故なら人を殺すモリの人など今までどこにも居なかったのだから。だから自分が最後の、森の人なのだ。しかし剣を手にしたモリの人など居るはずもないのだ。モリの人はもうこれで居なくなってしまった…殺人を犯した夜から杖を捨て、痛みのためにずっと這い回って生活したせいか四肢はおかしく突き出て、その姿は最早人と言うよりも獣であった。ついに女は肉体的な最後を悟り、木の洞に胎児のように丸まると息を引き取った。膨大な菌類が女の骸を苗床に歌っているのを聴きながらヌイと化した女はそれでも、尚も森を歩き回り、季節や時節をも移動し続けた。…恐るべきことに旅は時空間を超えて続いていたのだ。ある時は出産の祝福を与える聖なるヌイに、またある時は声聞きになるかならないかの瀬戸際に居る女の目を覆う闇のヌイに、そして常に声聞きに警告しようと神秘の逃げ道を教えるヌイとして種々の機会を見ては合図した。しかしある地点を超えてからの声聞きたちは皆、剣を手放さず常に怯えていたため、ヌイたちは金属の持つ反射に照らし出されて声を出せず、警告を伝えることが出来ずにいた。ヌイと化した女は何故自分がここまで日々森の人の声聞きに声を聴かせるために語り続けるのかを既に忘却していたが、それでも助かる道を語り続けた。
女は霊魂となって『今』でも森の中、様々の時間の一点に向かって語り掛けているのだ、よって森は今でも続いている、焚火は今も尚燃えている…正真正銘最後となった森の人の時代は、今でも続いている。