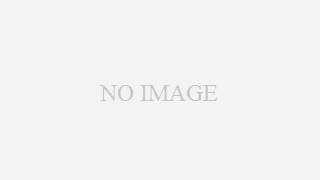今思えば彼は残暑の蜃気楼が作り出した幻影だったのかもしれない。
夜空の散歩人を自称する老人は、やる事もなく真昼の畑を眺めていた私を見つけて言った。
「私は夜空を歩きますよ、夜空は道しるべが無くて、然るべき計器がなければ飛行機だってうかつに歩けないなんてみんなは思い込んでいますがね、夜空には地上とおんなじ道、いやそれ以上の光の迷路が作られているんです」
土埃の立つ道端に腰かけた老人は、日差しを遮りながら静かに笑う、秘密の地図、夜空に現れる秘密の地図について教えてあげましょうと彼は嘯く。
「ほら、見てごらんなさい、鳥よけの反射鏡、銀色に輝く紐が畑に張り巡らされていますでしょう?」
彼が指さすほうを見ると、それが毎年の事とあってか鳥たちは、人間様の農作業への執念でもある反射鏡の光など意にも介さずに飛び回り、あまつさえ鳥よけの紐の上で、銀色に鋭く輝く光をらんらんとその小さな体に受けて、群れに群れて寛いで歌っている。
「夜のことは誰も知りませんからね」と彼は言う。
「秋の間にだけ現れる星空の地図、畑に張り巡らされた銀色の紐が、昼の間に浴びた光を夜空に反射させ、夜空へと人を誘うのですよ」と彼は言う。
およそ道と呼ばれるものすべてが、区画整備されたものすべてが、昼の光や活力を夜空に反射させているという事実を知る者はそうはいまい、と言いたいらしい。
夜空を歩く老人は静かに微笑んだ「この畑くらいの小さな迷路だったら、あなたでも歩けますよ、あなたの足でも夜空の迷路を歩いてみることができますよ、なに、杖をついていたって大丈夫、この畑に張り巡らされた鳥よけの紐をちゃんと覚えて居れば帰ってこれるんです」
あなたどこかへ行きたいのでしょう?
家に居づらいのでしょう?
にもかかわらず、家へ戻りたいのでしょう。
暗にそんな言葉を含んで彼はまた続けた「どんな役立たずでも、きちんと物事を成し遂げられるってことを自覚していなきゃいけません、はは、厳しい事でしょうが、そのためには訓練が必要なんです」
老人はもっともらしく自らの発言に頷いてからスタスタと去っていった、今思えば彼は残暑の蜃気楼が作り出した、自責の幻影だったのかもしれない。
けれども私は庭から出て、畑一面に張り巡らされた銀色の紐をくまなく観察した、何せ夜空には体一つ以外の何をも持っていけないと聞かされていたのだ。
私には還るべきところがない、しかし帰りたい場所はある、畑を荒らす小鳥たちを手で追い払いながら私は鳥よけの紐が、どうやら一つのおおきな図形を形作っているらしいことを発見した。
それは星形だった、☆、これならば一巡りすれば帰ってくることができる、星のそれぞれの角には反射鏡が立てられていた。
原因は、それが昼に見た、地面の図形であったことだ。
真夜中になった。体一つ以外の何をも持っていてはいけないと聞かされていた私は、目に見えぬ罪悪感をはらすため、彼の指示通り一糸まとわぬ姿となり、庭に出て寝ころんだ。
すると意外なことにすぐに体は浮き上がり、夢の中のような心地になって私は夜空を下に歩いていた、頭上には煌めく街明かりが竜宮城か何かのように非現実的な美しさを漂わせていた。
「そうですよねえ、あなたはまだ夢では杖をついていないんですから歩けるはずです、夢の中までは痛みは追ってこないんでしょう?」
後ろから聞き覚えのある声がして振り向くとそこにはかの老人が居た、あなたも夜空の散歩人ですよと彼は微笑み、指をさした。
夜空一面に、昼間見たときには小さな畑に張り巡らされていた鳥よけの紐の光が満ち溢れていた、あっと私は息を飲んだ。
「比率ですよ、比率の差です、地球からすると宇宙は広大でしょう?夏の大三角形のあたりにほら、ちょうど反射鏡があります、あれをゴールにしましょう、ほうら駆け出してごらんなさい」
老人の言う言葉に私は愕然となった、何故なら、身体は夢のようにうやむやになっても歩く速度は決して早くはならなかったのだ。
無茶です、と私は夜空のただなかに実体も無くあてずっぽうに浮遊しながらも反論した、光の速さで星形を移動したって、夜空じゅうを駆け巡るには一体どのくらいの時間がかかると思っているのですかと叫んだ。
私の叫びは宇宙の隅々に散っていった、叫びもまた目に見えて、それら一個一個は星の形をしていた、どうりで尖っているはずだと私はどこか投げやりな気持ちで自分の叫びの星屑を眺めながら涙した。
しばらくすると、自称、夜空の散歩人の老人は言った。
「人間というのは我がままなもので、辛くなるとどこかへ行きたくなるものですよ、それも一日二日というわけではなくもっと長く行方をくらませたくなるものです、神隠しとか昔は言いましてね、数年、なかには数十年たつとふらふらと人里に帰ってきたりするものです、あなたが畑をぼうっと眺めていることは夜空からよく見えましたよ、夜空の星の一つになる、星座の一つになるなんてのもなかなか、ロマンあふれる失踪ではありませんか、どうです?夜空の散歩人になってみるというのは、そのほうがあなたのことを理解してくれますよ、みんな」
静かに笑う老人を私は突飛ばそうとしたが、身体自体があやふやなので力が入らず、私は転倒した。
杖を握らなくては…と、どのくらい強い気持ちで思ったのかは自分でもわからなかった。
だがその拍子に、とっさに私の手は実体のある何かを確かに握った、それは昼の間、相反する気持ちで握っていた杖そのものだった。
杖を手に握ったということがもたらす意識の移行によってか私は、足のつかない夜空一面に向かって杖を大きく振りかざし、力いっぱい…私から見える範囲で夏の大三角形を含むそのすべてのパノラマいっぱいに星形を描いた、これでもう夜空を旅したということになるでしょうと涙声で言うともうそこは、涙を吸って湿った土の上だった、静かな夜の庭だった。
鈴虫たちがおかえりと言っているのが聞こえ、頭の上には夜空が広がっていた。
「これはやられましたねえ」という、件のしわがれ声がしたように思ったが、この、畑を荒らす狐のような老人に一杯食わされかけたといって、実体のあやふやな彼に罪を着せるのも気が引けた。
何故なら彼は残暑の蜃気楼が作り出した、私の幻影だったのかもしれないからだ、かくして私は土を払い落とすと裸のまま家へ入り、杖を握りしめたまま眠った。