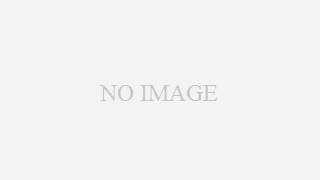世界が終りかけるというやむを得ない事情があって、男は職を変えた、もともとは料理人だった、多くの人間がウイルス珍事に振り回されたように彼もまた身の振り方を一時的に考えての事だった。調理方法はレシピ通りにやればいい、味もレシピ通り、そう聞いて男は病院内の調理室に貼られた一枚の紙を見た、でもこれは味がするんだろうかと思ったが男は指示に従い調理し始めた。50人分の料理を一度に作るという作業は並大抵のものではない、しかしそれを手分けしてやれば、いつの間にか慣れるもので皆マスクの奥で小声で話しながら作業を進めていた。
灰色の建物は街のはずれに建っていて、大きな運河が見える、空も曇っているからまるで世界中から色が消えたみたいだと男は思った。
タンパク質、糖質、食物繊維、塩分…塩分濃度は規定値を超えないこと、ここにいる人たちはレストランに来ているんじゃないんだから!というのが栄養士の口癖だった、一応メニューはそれらしく調整されていた、食べ物らしく調整されていた、定食屋のようなメニュー。男はそれらにミキサーをかけていた、この国の人間ならだれでも知っているであろう味にミキサーをかけたり、柔らかく煮込んだりした、なぜかそうされた料理は悲しみをたたえた様子で男を見返してきたが、その視線はとても薄いものだったので、男はそれを無視することができた。
料理一皿にも魂が宿る。
そんな口癖の料理長のもとで働いていた男は運河の街からほど近いレストランで長い事料理を教わった、その一皿に驚きがあるか否か、その一皿に驚きを添えるならばどの味が適切か、レモン一切れだったり塩一振り、香草や、料理を最後に火であぶるかどうか。また季節によって人の舌も変化する、春には口の中で広がるものを、夏には酸味のあるものを、秋は大体なんだって喜んで食べるのが生き物の性(さが)であるので多少の手抜きは神様が許してくれると料理長はよく笑っていた。
季節だけではない、雨の日にはビアンコ…白いソースのものが適切で、太陽のさんさんと降り注ぐ時にはロッソ…赤いソースにするんだと口酸っぱく男を諭したものだった。
「人間ってのは一見一人一人に見えても全体全部でつながってる、人間単体で独立して個人個人で生きてなんかいないんだ、天気や季節、そういう環境だけじゃない、その場の過去や未来ともつながっている、だからその場所ではこれが美味しくても、あの場所ではそうはいかない、その空気を見定めて、魂の驚きを与えてやるのが料理人ってものなんだ」
レストランの料理は一皿単位で作るものだった、一皿単位で塩分濃度を決める、一皿にはあふれんばかりの風味が押し込まれている。
対して病院の一皿は50皿単位で作るものだった、50皿単位で塩分濃度を決める…もとい、決まった塩分濃度の値を超過しないように注意を払う、風味は化学調味料を使う、塩分濃度を上げにくいのでその分化学調味料で補うのだ、この使用については塩分のそれよりもだいぶ規則が緩かった。
灰色の建物で調理している男は、レストラン時代を思い出しながらも院内調理長を呼んだ、一口掬って食べてみてからこれでいいか尋ねると、調理長は首を振る「あのねえこれじゃ味がしないでしょ」、男は体温計に酷似した塩分測量機を片手に、塩を振る、はじめから風味のしないものを細部まで味わおうとして入れた塩が薄い、となれば増やすまでだ、少なくとも塩味を感じ取れるくらいには…男は念じながら塩を足した。…と、塩分測量機が小さくアラームを発する、院内調理長は肩をすくめて見せた、「あなたねえ」もともと料理人だったんでしょとまでは言わない様子なのを男はかえって恥じ入りたい気持ちで床を見つめてやり過ごしていた、床もまた灰色に磨かれていた、色のない世界には風味もなかったのだ。
図に書いてみようと男は思った、運河のそばを帰宅がてらジョギングしながら考えたのだ、それはある種のひらめきのように思えた、もはや何をどうすれば病院の一皿が完成するのか、この元料理人の男にはわからなくなっていた。川面には数隻の船があって、何かの合図をし合っているようだったがそれは川岸からはわからなかった、急に、今すぐに病院食の味付け、塩分適正値を知らなければこの船たちを川岸で力なく、部外者の体で見つめているのとまったく同じことが現在の職場でも起こってしまうような嫌な予感がして男は立ち止まり、土手に腰かけてリュックサックからメモを取り出した。
メモの右半分にレストランの一皿を描いた、レストランの一皿は何でできているかを細かく書き込んだ。
・その日の天気
・その時節の気候
・お客の性別
・秘密の調味料…けれど全部天然のもので料理長や時に自分が市場から買いだしてくるもの
・火力の強いガスコンロ…一般家庭では使わないほど強く、逆にとても繊細な弱火も出せるもの
・一皿を仕上げようという気力、一皿を食べた人を驚かそうという気力、新しくおいしいものを作りたいと願う気力
・精神的栄養になるかどうか
風味100%、そのうち塩5%、オイル10%、香料5%…つまり120%のものを、質量保存の法則上許す限り詰め込むのだ。目に見えない微細な粒子が…作り手である自分の魂とも言えるべきものが、その一皿を食べる人の口に合うかどうかが、いい料理とそうでない料理の分かれ目だった。風味が100という限界値に達している、これを目指すのが料理の決まりだった、男は頷いた、一方病院食には風味という概念は無かった。
左半分に病院食の作り方を書いた。
・塩分濃度が規定値を超えないこと
・バランスの取れた栄養
・適切な量、適切な柔らかさ
・肉体的栄養に適するかどうか
その他に書き記すべきものはなかった、一番重大なのが一皿の質量であった、レストランでの一皿は風味やらなにやら魂も含めてとにかく破裂しそうなほどに込められている、120%なのに対して病院の一皿には込められるというよりもすべてが減らされている感じがした、体感として病院食は、レストランでの一皿の10%くらいだと男はつぶやいた、レストランの一皿の10分の一が病院食一皿の質量なのである。よって何か付け足そうと思っても、塩分もうかつに追加出来ない、塩分は規定値を考えるならば自分が足したいと思う量よりもさらに-5%ほど減らさなければならない。
人間が本当に何でできているのかは男にはわからなかった、栄養素を考える限り病院食のそれは物理的には健康に良いと証明されているようだった、しかし、人間は本当は風や太陽や草や目の前で無邪気に飛ぶ羽虫のその羽の音でできているといっても過言ではないと男は思い、頭を抱えた。
こんなにも質量の無いものを食べて病人たちは生きてゆけるのだろうか?
これを食べていたら病気は良くなるどころか、死へと急ぐための供物のような気すらしてくる。それは有り体な意味での、料理人が調理人を馬鹿にする思想よりも遥かに男を震撼させるものだった、男は心のどこかで恐れていた、目に見えない味付け、風味という味わい尽くしがたいもの…そういった料理に宿る魂を人間が食べ、ある意味では料理人の魂をお客は食べ、魂の聖なる共食いが起こるあの場所、レストランだからこそ旨いと感じられる料理が自分から遠のくのを男は恐れていた。病院調理を見下しているのだろうかと自問したが本音は大いに異なっていた、この病院調理の塩梅に慣れてしまうことを大いに恐れていた、自分自身も病院食のような質量の全く無い、魂の欠けたような存在になってしまう気がして、男は思わず目を瞑った。
翌朝仕事場に行くと栄養士が来て言った、「新しい患者さんが来るから、その人用のメニューはこれね」、周りで失笑が起こった、「この人信じられない、野菜全部だめだってさ!どういう生活してきたのよ、お菓子とお肉は食べたいんだって、もう笑っちゃうよね、そんなんだから病気になるんでしょうが!」、皆は調理の手を緩めることなく機械的にすべてを捌きながら患者の特徴を述べては小突き合って笑っていた、男はそれを尻目に焼いた肉をミキサーにかけた。
何故このように皆が患者を笑えるのか多少理解できたが、同時に少なからず疑問ではあった、基本的にこの仕事は患者には対面しないようになっているのだ、我々はただ規定に従って調理するのみ、すべてがウイルスに支配されてからというものレストランは閑古鳥になり、男はこの職場に来た、男とて、どんなに質量の薄い食事でも摂らなければ死んでしまうのである、この病院に収容されている多くの患者たちと同じように。偏食の患者は調理の手間がかかるというので嫌われていたのだ、嫌う要領で、対面せずとも悪いやつに仕立て上げて笑いものにしているらしかった。
本当に患者など実在するのだろうかと、食事を、院内調理長のさらに上役、総監督でもある病院院長へ、本日の見本として持ってゆくエレベーターの中で男は考えた、誰ともすれ違わないこの病棟に収容されているのはほとんどが後期高齢者だという、もう自力では動けない後期高齢者があの薄い食事、むしろ逆に食するものの魂を奪うようなブラックホール状の…何も無い食事を口にしているのを男は思い浮かべ、院長室のドアをノックした、院長がその場に居ながらも無言なのはいつものことなのでそのままカートに積んだ「完成品」を出す、失礼します以外の言葉を男は発さなかった、院長は窓に向かってしつらえてある机の上に、貼りつかんばかりに顔を向けていて、常に外の鈍い光のせいで逆光に照らされ、ウンともすんとも言わないその暗い存在自体が影のようでもあった。
引きこもりの息子、もともとは優等生…それに対して食事を与える母親、でも魂の聖なる共食いは起こらない、そんな文句が院長の影を見ているさ中に心にふいに浮かび、男はつい、誰にも聞き取られないほど小さく笑ってしまった、しまった、と思った、しかし影は相変わらず変化しなかった、今のこの瞬間、空気は変動したはずだが影は微塵も変動しなかった。
あれは死だ、一種の死だ、と男は思った。
しかし生きるための食事を自分は作っているのだ、世界があやうく終わりかけているような世の中で職を変えたくはなかった、それは迂闊だと男は自分を制した。生きるための食事を自分は作っているのだ、空のカートを調理室に引き下げる道すがら繰り返し強く念じたとき、普段なら静かで、消毒液と篭った化学調味料の匂い以外なにも…生命の気配が一切漂わないこの灰色の廊下に叫び声が響き渡った。
…それを言葉に翻訳することは、物理的にはおよそ不可能に思われた、獣か、あるいはもっと…怨霊のような…そういった魂の叫びであった、ある意味男は感動した、このようなむしろ命が削り取られる場所でまだこれだけの、叫ぶほどの魂の鼓動があったのかと男は意外に思い、それが生じた方向を見定めようとじっと前方を見つめた。しばらくそうやって唖然として立ち尽くしていると、閉じられた一つの病室のドアの曇りガラスに何かが叩きつけられるのが見えた、それがさっき自分が調理、もとい、塩分調整を行い、ミキサーをかけた50皿のうちの一皿だと気づいたのは投げられた飛沫が液体状になってそこを、ドアの内側つたうのが、曇りガラス越しに見えたからだった、その時再度叫び声が上がった、さっきよりももっともっと強烈な叫びが、強烈な一声が。
こんなもん食えるか、俺は生きているんだ、こんななにもない部屋に閉じ込めてベッドに縛り付けて何を考えている、自分の糞の匂いを嗅ぎながら溶けた飯をなんで食わされなきゃならないんだ、おい、聞こえるか、そこのお前、お前だよ、お前も今生きて世界を見ているんだろう?この灰色の世界を!お前は自分と俺が全くの無関係だと思っていやがるみたいだな、それぞれが独立した存在だってな、大間違いだぞ!ある意味では俺はお前なんだ、俺は、俺は昔料理人をしていたんだ、こんなのは料理じゃねえ、餌ですらねえ、ウイルスなんざこわかねえよ、たのむ、迷惑はかけねえ、俺を殺してくれ、頼む、体中がいてえんだよ、痛くて痛くて動けねえんだ、なあ、わかるか、俺はここにいる!!!
これらの思いがたった一声の叫びに籠っていた、120%の質量で叫びの中に籠っていたのが男には聴こえたのだ、実際にはそれは寝たきりの人間から発せられた母音の一定に伸びた音だった、赤い紅い音だった、血しぶきというよりももっと何か別のもの、ロッソ!ロッソ!赤い紅いソース、トマトソースと魚介のブイヤベース!新鮮な肉!タコ、赤い赤いワインでもいい、とにかくそういうものだった、殺人の赤というよりも出産時に母親から流れ出る、子宮の聖なる血のようなもの、胎盤のようなもの、赤ん坊のようなもの。
魂の聖なる共食いを示す深い深い叫びを男は愕然としながら聞いていた。
今確実に、男は扉の向こうの人間と魂の共食いをしていた。
自分の頬に涙がこぼれ落ちるのを男は感じた、透明の涙、透明というのは白、ビアンコ!白い涙は姿を見せぬ患者の赤い叫びと呼応し、男を揺るがした。
赤と白の共鳴を男はまざまざと体感しながら、それでもなお、冷静に考えた、ただの調理係である自分がこのドアを開けることは不可能だった、首では済まない可能性がある、懲罰、医療上、過失…そういった法的な文言がたちまちに男から色彩を消してゆき、赤と白の共鳴をも、無かったことのように清めていった。
廊下はもとのように灰色になり、病院内の質量はマイナスに保たれた、先ほどの爆発は一個の宇宙すら誕生しそうなほどであったのに、人間の制約は人間にとってすべてを失わせるものである、こんなものを我々は信じて崇めているのかと男は自問自答し、調理室へと戻っていった。
夕暮れの運河の街は妙に清らかに見えたが、実は殺人ウイルスだらけなのだろうかと男は考えながら走った。
…人が望まないことをし続けるのは悪行だ、今自分は悪行をしながら生きているのか?男は自責の念で苦しくなった、しかし一方で…信じがたい事だがあの食事を食べて退院してゆくものもゼロではなかった、人間は物質的な質量だけである程度までは生きられるのは確かだった、必ずしも悪行とは言えず、けれどもある地点からは全くもって善行(ぜんぎょう)とは称し難いこの仕事を、いましばらく続けることを男は思い、首を振った、是という意味で首を振ったのだった。抵抗する魂を自覚することでなんとか、自分が自分でいられることを望んでいたのだ、男は走り続け、その影は夕やみに光となって消えていった。