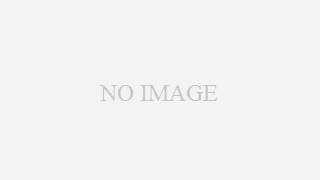「何なんですかこれは!」
ジーンズ姿の青年は息を荒くして編集室に駆け込んできた。「おかしいですよね、こんな風に取材されてたなんて、何で僕の事をかわいそうな人扱いするんですか!」、一瞬室内は静まり返ったがまたにわかにいつものざわめきが蘇り、何事もなかったかのように時間が流れ始めた。
タバコのにおいの染みついた煤けた編集室の一角で、初老の男は自分と対峙する青年を見据えていたが、同時に仕事をこなすために受話器に耳を当てていた。しかし青年を諭すように青年の発言に対して頷いて見せた。
わかってるとでも言いたげなその表情すらなんだか役者めいていて、しかも青年よりも一枚も二枚も上手の演者であるために余計に、話など本来聞いていないということが逆にありありと見て取れた。それなのに誰も制することが出来なかった。話し合いなど成立し得ないことを青年も含め誰もがわかっていた…わかっていたが青年は本を机に叩きつけて言った。通話が終わらないことを見越しており、せめて怒鳴る事くらいさせてほしい、そんな気持ちに駆られていたのだ。
「車中泊をしてるって確かに僕は言いました、あなたが路上生活者…いや、車中、車上生活者のルポルタージュを書いてるってことも、それが番組になってるってことも、僕は聞きました、僕の事は番組には流さないでくださいっていう約束も守ってもらいました」
青年ははじめのうちこそ大声で話していたがすぐに俯きがちになり、小さく話し出した、初老の男は首を振ってそれを制した。あいにくこの騒がしい場所で受話器片手にではとても聞こえない、聞き取れないという意思表示であった、それは既にどこか大きい声ではっきりと話せという命令の雰囲気を帯びていた。
俺の言うとおりにしろと促されていることに苛立ちを感じ、青年はもう一度、手にしている本で机を叩いた。物の鳴り響く音が編集室に広がったが皆故意にそれを無視するかのようにそれぞれに忙しそうに動き回り、その音を消した。
ここはいわばひとつの生命体の巣であったのだ。その決定権を持つ人間はこの部屋には居なかった。本来どこにもいないのかもしれなかった。が、異質な振る舞いをかき消そうとする昆虫じみた思考回路に全体全部が絡めとられているのを青年は感じ、身震いした。
青年が自分の言うとおりに大声で話さないこと、しゃべってしまえばさっさと帰るだろうにそれをせず、今度は口をつぐんでいつまでも立ち去りそうにない事をようやく悟った初老の男は、忌々しいのを顔に出すまい、尻尾を出すまいと心得て受話器を置いて立ち上がった。「場所を変えましょう」、敢えて丁寧に青年に言うと初老の男は先に歩き出した。
公園のベンチに腰を下ろすと初老の男は促した。「何か思っていることがあるのなら我々に教えてください」言葉は低姿勢だがそれが一層冷たく響いた。青年は少し間をあけて自分も腰かけ、地面の規則正しいレンガ道を睨みつけながら言った。「こっちからどんなに連絡しても無視されたのでここまで来ました、メールでも、電話でも取り次げないと言われたので僕はここまで来ました」青年は初老の男のほうを見ないようにしているらしかった、青年は相手が応答する前に言った。
「適当に謝らないでください!そういうのはうんざりなんです!忙しいとか外部の者とのやり取りには制限があるとかそういうありきたりな、表面上の、セリフ、みたいなものを聞かされるのはうんざりなんです!僕が何で怒っているのか本当はわかってるでしょう?僕は、好きで車上生活してるんです、それをなんでああいうふうな書き方するんですか」
初老の男は肩をすくめて見せた。「取材したのは私です、あなたは車上生活をしていた、それを取材し、書いたのは私です、私の書きたいように書くのは普通のことじゃありませんか?あなたの指示でモノを書くなんてことは出来ないんです、私は一介の記者に過ぎませんから、でも、至らないことがあったのは…」言い終わらないうちにまた青年はそれを制した。
「確かに僕は僕の人生まで喋りました!それは僕の落ち度です、僕が高校でいじめに遭って中退したことも…でもそれを絡めて僕が、人間社会から追い出された哀れな人間として、人間未満の人間として、土地を追い出されて車で生活せざるを得ないっていう風に物語を締めくくるっていうのはどうなんですか?ほかの人のだって読みましたけどみんな酷く書かれてますよね?僕は今結構楽しくやってるんですよ、アパートに居た時よりも今のほうが絶対気楽です、そういう人だってたくさん居ますよ、それに…何で土地を持って通勤してってことを価値観の基準にするのか本当に疑問なんです、それって何なんですか?それが出来なきゃ人間じゃないみたいなあの書き方、何なんですか?ほら、読んでくださいよここです、『青年は思春期に人間社会に挫折して以来社会を拒み、働いていた会社も辞め、今はアルバイトをしながら車の中で生活している、戻りたくても戻れない人間社会を夢見ながら一台の車に追い込まれた青年の、悲痛な叫びは都会の片隅の駐車場にこだましているー』って何なんですかほんと、僕は正直に喋りましたよ、素直に、今楽しいって!それなのになぜこういう書き方するんですか、どれもみんなこんな風に締めくくってますよね、『この異常な生活は、社会のゆがみの一端である』って、なんでですか…何なんですか!」
その通りじゃないかと初老の男は吹き出したいのをこらえていたがもう口元の微笑みは隠せなかった。青年が純粋に怒りを露にすればするほど哀れでならなかったからだ。そういえばこんな風にいじめられてたやつがいたなあ、クラスに一人か二人はいつも居たもんだと心の片隅で回想しながら、そいつらが素直に怒ると周りのやつらはみんな、呆れてこんな風に笑ってしまったものだっけと穏やかですらある気持ちで妙に納得していた。初老の男は回想にふける頭を下げながら言った「いやあすみません、正直申しまして、私共には理解が出来ていませんでした、何しろ古い人間なもので、固定概念に囚われているのですよ、若い方の幸福というものは本当に測りがたいものです」特にお前みたいなクズの言う主観的幸福はな、と内心付け足しながら、平に平にご容赦くださいと謝罪めいたことを体現する姿勢をとった。平日の昼間、鳩が遠くで一斉に力なく鳴いている声が灰色に木霊していた。
若い、という事以外に社会的にも生物学的にも取柄の無い青年は虚を突かれた思いで一瞬にして怯んだ。無論それが彼の若さ故の甘さでもあった…自分の蒸発した父親以上の歳かさの人間にこうも頭を下げられると、自分の主張が本当に的を得ているのかどうかはさておき、人間として接してくれているということそのものへの根源的喜びがふつふつと湧き上がってきていた。皮肉にもこの喜びを引き出すのが巧みであるがゆえに相手は記者稼業をしており、自分はべらべらと、自らの生活…社会の中に於いては異端の生活を吐露してしまったという数か月前の過去をすでに、唐突な謝罪に面食らった青年は忘却しかかっていた。
この社会についてのあれこれ…住所不特定の危うさや、資産税の制度からの抜け穴である車上生活、平均的な生活を全員がするためにはみんなが背負うべきものをそれぞれに担わなければならない成り立ちについて、この頭の薄弱な青年にわざわざ話して聞かせてやるのも馬鹿馬鹿しいと初老の男は思った。第一もう取材を済ませた相手であり、手ごたえの無い一人の無知な若者に過ぎないこの青年には用が無かった。手ごたえ、というのは記者独自の勘で、次の取材につながるような面白さを含んだ人間の場合は、確かに…いろんな意味で学ぶことも多いのも事実ではある、再度の面会を求めたりもする。「こちらは数十年記者をしていますが、新しい考えというものは我々には不可欠ですが、にもかかわらず、新しい考えを理解できないことが多々あるのです」例えば目の前の彼とは別の車上生活者の若者は商才の機知に富んでおり、また別の夫婦には、車上生活だというのに赤ん坊が生まれそうになっている…無論この場合大多数が好むのは前者のような機転の利く突飛なエリートの若者ではなく愚鈍な人間の哀れな醜聞である。本当の意味での切実な叫びなど一切不要だった。作られた意味での切実な叫びというのはいつも悲痛な叫びであって魂の喜びからほとばしるものを指したりはしない。ああ、次の取材に行かないとなあと思いながら青年に目を向けた、初老の男は畳みかけるように言った。「本当にすみませんでした、我々のような、記者集団というものはまことに…昨今の言葉で言うならば無知な老害、なんですよ、いや、本当にすまない」取材は演技である、青年は最後の言葉に少なからず動揺し、初老の男をはじめてまっすぐに見つめた、手に持っている本が震えていた。
もう出版してしまったものはこちらだけではどうしようもできない、今回ご指摘いただいたことを次の本に添えておく、そういう業務上の口約束を平身低頭してみせてから、初老の男と青年の、名もなき数分間の会合は事もなく終わった。初老の男は編集室に戻るとため息をついた。同僚がやってきて笑った。「居ますよねああいうの」、「ああいうのをなんて言ったらいいんだろ」、応じながら考えた。
「ポエマーだな」同僚が笑いながら言った。的を得ていると初老の男は思った。主観的過ぎる人間というのが社会には一定数居る。そしてこの社会はすべてを含めて上限が存在している。主観的過ぎる人間たちにはこのことが理解出来ない、ポエムで金が湧くと本気で思ってやがる。初老の男は苦々しく笑った。「老害って言っときましたよ、俺は老害だから勘弁しといてくれって」編集室はひとつの生命体である…誰というわけでもなく一斉にどっと笑い声があがった。それが傍目には随分と投げやりに聞こえることを、客観的には異様だということをその場にいる人間は誰一人として気が付かないでいた。謙る事には皆慣れていたのだ、劇中劇には慣れ切っていたのだ。
どういうわけだかこの職場にもポエマーがたまに入ってくる。社会の仕組みや枠組み、人間社会が数字も含めてどのように動いているのかの摂理を全く主観的に無視するタイプだ。自分の主観的思想が社会のそれよりも偉いと根源的には思っている実は甚だ傲慢なタイプだ。外見や振る舞いは大人しくても、人間社会を軽んじているという点では無能で傲慢なタイプだ…初老の男は考えながら、虫に触れた時の女のように異質なものへの嫌悪感を募らせていた。別に若いとか年寄りだとかではない、いつの時代にも一定数、ポエマー、言ってしまえば主観主義というのは居る。彼らの傲慢が鼻につくのはそれ以外の人間の元来の性(さが)であると改めて思った。人間社会に重きを置かない人間の傲慢さをどう捌いたら世の中のためになるだろうか?もっとも質の悪いのは、人間社会が傲慢であると信じ切っていて自分はそれに立ち向かうために記者になったのだと自称しているタイプだと彼は思った。女ならば悲劇のヒロイン、男ならば勇猛果敢な孤独なヒーロー気取り…「虫唾が走る」初老の男は幾人もの自称ジャーナリストに出会ってきたし、ひどい時には狂信的でさえある彼らの教育係にさせられるという憂い目にも遭った。うんざりだった。その気持ちが周囲にそれとなく伝播したのか、彼らはいつもいつの間にか職場いじめらしきものにあって解雇寸前で自ら会社を辞めて行くのだった。「いい気味だ、守るべき人間社会の客観的秩序を軽視するからああいう目に遭うんだ」気持ちに整理がついたのか彼は口元に笑みを浮かべた。
「主観主義はただのポエマーだ、ジャーナリストじゃない」初老の男はまた、次のカモたち、次の取材先へと電話をかけ始めた。