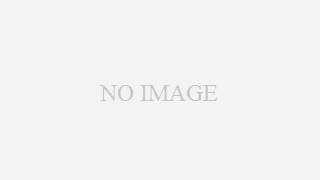イスカリオテのユダがそうであったように生贄の血を貪欲にたらふく飲んだ魔物は家の戸口で首を括って死んでいた。部屋の奥にはつるりとした十字架があり、それだけが彼の人生を見守っていた。おびただしい数の画像や動画やその他の証拠品はすべて除去されるか捨てられており、この男が如何なる趣味趣向の持ち主であったのかを物語るものは何一つ残されていなかった。男は死んだ後に目を覚まし、あたりを見回した。雑木林が延々と続いているらしく、空は朝焼け前なのか夕暮れ前なのか…光を内包しているものの暗かった。死後世界と思しき地面には土を穿って出来た無数の穴が開いておりそのどれもから子供が顔をのぞかせているのが見えた。途端に死んだ男はぞくりとした。身体を失った自分が尚も激しい情欲を宿していることをふと察知して訝しんだ。すると男とも女ともつかない声がして振り向いた。「だれ?」というその言葉を言ったのが自分自身であると悟った男は自分の両手を見つめてあっと小さく叫んだ…彼は小さな子供になっていたのだ。「やっぱりここに来てしまったんだね」声の主はそう言って今や死後子供と化した彼を撫でたらしかった。「君は苦しみに選ばれているんだよ、生まれながらに生命摂理への裏切りの神秘を宿している、裏切らないように生きるにはそれなりの気力が必要だ…君は自分自身の情欲に身を投じてしまった、欲に目がくらんで裏切りを選んでしまった、今度は選ばずにまっとうすることが出来るかい?裏切りを宿したまま業火に焼かれながら生きることの神秘を全うできるかな?」かつて一種の魔物であった男…であるところの子供は声の問いに素直に頷いた。すると空が赤らみ、一筋の光の中、生命の波の中に彼は再び連れ去られたのだった。
「さあ、こっちに来るんだ、精霊を宿すにはどうしたらいいか教えてあげよう」壮年の司祭は言った。一方、生を新たにした元魔物の首吊り男は現世に於いてまだ年端もゆかぬ子供だった。司祭は彼の小さな腕を引くと祈りの小部屋へ入っていった。春の日差しが充満する殺風景な部屋の中で司祭と子供は向き直った。司祭は独特に息を弾ませ、その目は異様に光っており、その場の雰囲気からして何かこれから良くないことが起こるのを子供は勘づいていた。司祭はもどかしげに椅子に腰かけると勢いよく祭服をまくり上げ、にわかに足を投げ出すと子供を手招きして足を揉ませ、だんだんとその手を股間へと導いた。部屋は静まり返り、司祭の荒い息遣いだけがこだました。子供はおそるおそる…白髪交じりの陰毛に覆われて勃起した司祭の陰茎を見つめた。若干の恐怖と言い知れぬ嫌悪感が彼を駆け抜け、思わずぎゃっと叫びそうになるのを司祭は彼の口に手を当てて制した。「いいかい、今私は苦しい、痛いくらいに苦しい、私は渇いている、君に潤してほしいと願っているんだ、君は私のために足を揉んでくれた、身体を触ってくれた、いい子だ、そのまま…そのまま…」
その後に及んだ一連の顛末について子供は恐れ、一人呟いた。「お母さんに怒られる…」そんなことを繰り返し繰り返し考え、底知れぬ罪悪感に泣きながら帰宅したが元々が脆弱な質であるために両親は何が起こったのかも気付かずにいた。彼が泣いているのもいつものことだったし怯えているのもいつものことだったからだ。この子供は同じ年頃の子供よりもすべてに於いて弱く劣っていた。そういうわけで彼の両親たちは思想の軸を、世間的生物的なものから非現世的精神的なものへと移行させるべく、とりあえず教会と名のつくところへ子供を通わせたり自分たちも慎ましく…時に妙に明るく通ったりしていたのだった。この子供が何故かその壮年の司祭に気に入られているのを両親は内心誇らしく思っていた。他の子供よりもずっと覚えがいいと司祭はこの凡庸な子供を誉め、どう考えても落第しそうな彼の成績表を見ても瞬時に司祭の言葉を思い出し、両親は根気強く子供を励ました。子供はその間も頻繁に司祭の部屋に引きずられてゆくのだった。
何かがおかしいということにこの気の弱い子供は気付いていた。事がばれたのは運悪く子供好きの青年に対してだった。青年は壮年の司祭に耳打ちし、青くなった司祭はなけなしの金と子供を弄る権限をすっかり青年にやってしまうと同時に彼は一身上の都合という方便で教区を去っていった。子供は少年になっても司祭同様「子供好きの」青年のところに呼ばれて乱暴な扱いを受けていた。何度も何度も両親に話そうとしたがいつも家のドアの前で膨大な時間の歪みを体験し、その都度思い直すのだった。何もできない自分が彼ら両親をさらなる不幸のどん底に陥れることは神に対する冒涜のようにも思え、少年は、学校帰りに息の荒い青年の粗雑な腕に捕まると、怯えもあってかそのまま彼の部屋へと粛々とついてゆくのだった。少年の人生は既にある程度決定されており、この種の物事に関して少年自身が身体的に衝動を覚えるたびに、どんな夢想を思い浮かべるよりも強く壮年の司祭や乱暴な青年にされたことが反射的に思い浮かべてしまうようになった。一方少年が成長するにつれて子供好きの青年は次第に彼に興味を失い別の獲物へと去っていった。かくして少年自身が若者になったとき、最早自慰のたびにどんなに夢想しようとしても、どんな映像を見ようがどんな話を読もうが…彼の快楽にはおぞましい恐れや憎しみが付随し、その恐れとおぞましさを共有する相手を彼は探し求めるようになっていた…皮肉にもいつの間にか彼自身が従順な子供を求める男になっていた。彼はまたもや魔物の男になろうとしていた。
「神様…」それでも魔物になりかけているこの男は一人、自分の住むアパートで孤独に懇願していた。癒されることのない渇きを自分自身が宿していることに男は気が付いていた。射精というものが恐怖と憎悪と支配に彩られているということからは逃れようもなく、相変わらず通っている教会には年端もゆかぬ子供らが溢れ、その細い手足や柔らかな髪、まっすぐな瞳が彼をとらえるたびに男は自身に宿る悪魔に抵抗し、部屋に帰宅すると自らに鞭打つように成人した男女の結合を見て衝動を発散させようと努力した。だがネットというパンドラの箱はまさに悪魔の囁きにあふれており、実際に手出ししなければ何を考えても自由だと男をそそのかした…一度だけ…二度だけ…そんなつもりで幼児ポルノめいた(あるいは本物の)映像の数々を男は飲み込むように鑑賞し、時に涙すら浮かべながら身を震わせ達する日々が続いた。何故ならなるべく強い快楽を伴う射精をしたいという生命に必然的に付随した欲望は…彼にとって必然的に…なるべく強い嫌悪感となるべく強い罪悪感、そしてなるべく強い悲しみを引き起こすものでなければならなかったからだ。男は虐げられながら、一人夢想の中で子供を散々に虐げて過ごした。男の部屋には幽霊のように子供の笑い声と泣き声が響き、それが部屋の壁紙や床板にまでしみ込んでいるかのように思えた。彼は今や(ふたたび)子供という亡霊に憑りつかれており、そういった哀れな人間を食い物にする産物も、販売主義が加速してゆく中で大量生産されている世界に身を置いているがゆえになかなか這い出る事が出来ずにいた。『自分ひとりの夢想なのだから幼児性愛を無理やりに自分から引き剥がさなくったっていいじゃないか…』そんな思いも去来した。悪魔はそこかしこで彼を笑っていた。
「…あなたが好きです」目の前のとんでもない豚女に告白されてさしものこの男も固まっていた。教会の後片付けの後や係の手伝いの時に…その実子供ばかりを目で追っている彼に妙にいそいそと近づいてきては一言二言言葉を交わして嬉しそうに微笑んでいる豚によく似たこの肥満女がついに愛の告白をしたところだった。豚女は教会内では新参者で、当然ながら彼以外の男たちのうち誰も手を出そうなどという勇気あるものは居なかった。しかも魔物になりかけの彼が性的に奮起するのは子供の細い手足やつるりとした頑是ない顔に広がる笑顔だとか…泣き顔だったが、目の前の豚女には一切子供的な特徴は見当たらなかった。よしんば現実の女と付き合うにしても、不細工でもいいから小柄で細いのがいいと男は内心…それだけが幼児性愛者と化した自分が犯罪を犯すのを免れる道であるような気がして、理想の女性という夢想ではなく現実的な妥協として棒切れのような女がいいと決めていた。生憎豚女はこの妥協点にすら合致する身体的特徴すら見当たらなかった。夕日が豚女の無遠慮に突き出た乳房と教会の聖堂を照らしており、彼らの影はひとつに重なりかけていた。後ろのほうで信徒の老人たちが他人の春を嬉しそうにひそひそと囁き交わすのを感じ、男は自分がひどくみじめな気持ちでいるのに対して眼前の豚女が全く頓着せずに瞳を潤ませているのにひどく腹が立ってきていた。結局男は彼女を置いて…愛の告白に対し無言で帰宅した。
自分だけが世界でたった一人のような気がして魔物になりかけの男は暗い部屋に佇み、宙を見つめてため息をついた。豚女の件で教会内でからかわれるかもしれないという不安が彼を余計に孤独にさせているのだった。生理的に無理な相手に好かれるのは自分こそが生理的に不可能な相手を求めているからなのだろうか?男は自問し、祈った。いつも射精の暴力的衝動と祈りとの間には大きな…たぶん他の男のそれよりも拭い難い大きな隔たりがあって彼はそのことにひどく苦しみ、いっそ性機能の全てを失えば幸福に生きられるのではないかとまで思い詰めていた。もしかするとあの壮年の司祭も苦しんでいたのだろうか?あの青年も?夢想の中の性愛と現実のそれとを無理やりにでも一致させようとするのがあの二人ならば…自分はそのどちらかに折り合いをつけるべきなのだろうか?無論世界は豚女だけで構成されているはずもなく、男は世の中の約半分を構成する女という存在に手を伸ばしても差し支えないのを自覚してはいたが、それでも愛おしさを欠片でも感じとれる存在と結合したいと望むのは人間として当然のことであった。それならば小児性愛も許されるのではないだろうか…?人生の初めのうちはおぞましく恐ろしがっていた物事を今やこうして受け入れて性的興奮を伴って日々射精しているという肉体的事実が、ひょっとすると自分以外の誰か…要するに子供という存在にも当てはまるような気さえした。手を出すなら男児だろうが女児だろうがどちらでもかまわない。気の弱そうな子供を狙って口止めすればよい。なんなら金もやればいい。神様のことを本当に信じ込んでいるような気の弱い…そう、かつての自分のような人間を性の宴に誘い出したら首尾よくゆくのではないだろうか?
『何より自分は子供という存在を慈しんでいる。優しく触れてやることが出来る。はっきり言って自分はあのときの司祭よりもずっと若いしあの青年よりもずっと温厚だ。どうすればいいのかをよく心得ている。かの二人の反面教師のお陰でもっと愛を持って快楽に導いてやることが出来る。…これは性教育の一種なのだ。』悪魔の囁きは今や男を飲み込まんとしていた。そんなときに隣の部屋から押し殺した喘ぎ声が聞こえた。隣の若い夫婦がセックスしているのだ。
うらぶれたこの木造アパートにはどういうわけだかこの世の春を謳歌しているような若夫婦も住んでいた。上の子供は幼稚園に通っていたはずだと男は思い返していた。その子供を見かければ微笑んで手を振るようにしていたので夫婦もすっかり気を許して男が子供に近づいたり、彼らがほんの短い間遊んだりするのを何の不安もなく見守っていた。「最近の人はみんな冷たいけれど」いつだったか若夫婦は言っていた「あなたは本当に優しい人ですね」その時の彼らの屈託のない笑顔と、今隣で繰り広げられている動物的な交わりとを思うと男はむしろ気分が萎えてくるのだった。自分がこんな風になったのは果たして後天的な要因なのだろうか?それともやはりもともと子供にしか興味のない欠落者だからなのだろうか?それにしても夫婦が性を営んでいるということは幼稚園児はどこにいるのだろうか?男とも女ともつかぬ喘ぎ声は続いていた。自分が普通の男であったらこの声に何らかの感覚を刺激されるのだろうか…?では自分が普通ではないのは何故だろう?子供はどこだろう?性欲というものが他者と分かち合う事を目的とした営みならばなぜ、自分はそうでいられないのだろうか?わかっている、わかっている、子供は一方的な性の愛撫など根本的に全く求めていやしない。そんなことはわかりきっている…合致しようの無い性など性ではないのだ。障碍者や欠落者がそうであるように全体の何割に自分のような一種の不具者が存在するのだろうか?よくよく考えてみると、自分がこうであるのは健全な欲求を持った人間に何かを譲り渡したせいでもあるのではないだろうか?自分がおかしいのは健康な男女が、自分の性を侵食したからだ。そんな気がしてきて男は憤った。、生まれる前からある程度の運命は決まっていたのではないだろうか?自分は弱かったからまんまとあの司祭や青年の餌食になった、健康な男女…奴らは運命の罠にかからずに生き延びて正常な性を求め、弱者に何一つ返礼をしないまま野放図に生殖している!相変わらず夫婦は動物然として喘いでいる。
何故自分だけがこのような目に遭わなければならなかったのだろう?子供はどこだろう?あの幼稚園児は…男はドアをそっと開けて周囲を見回した、するとそこには紺色の園児服に身を包んだ件の幼児が突っ立っていた。子供は言った。「おじさん、遊んで!」贖いを受け取ったっていいはずだ。
眼前の園児は悪魔を纏ったこの男にとって極度に蠱惑的であった。トコトコと室内に入ってくると慣れ親しんだ男の脚に無邪気にくっついて笑った。「パパとママたまにちゅっちゅしてるの」幼児ながらに性事情を察知しているらしい子供はそのままアパートの小さな間取りをぐるぐる動き回った。何とでも言えそうだと男は思い、自分の手が震えるのを感じた。適当に話を合わせつつ理解不能な発言に付き合っているうちに、暗闇の中に浮かび上がる白い子供の手足が、最早人間ではないというほどに艶めかしく光るのが見え、子供特有の乳臭いような香りがこの孤独な部屋にいっぱいに漂った。男は鼻をひくひくさせて精一杯にそれを吸い込んだ。興奮と緊張とで全身が波打つような感覚に浸されるのを爪の先まで感じていた。感覚の麻痺した陶酔状態の男は、暗にこの幼児に性的に誘われているようにすら夢想しはじめていた。こんな幼児が自分と両親の性についての会話をしかけてくるという時点で…これが女だったら誘ってると断定できなくもない振る舞いを幼稚園児は確かにしていた。世の中の事情と決定的に異なるのは目の前にいるのは乳房の突き出た成人した女ではなく、子供、それも幼稚園児であるということ『だけ』だった。男は今まさに悪魔にそそのかされ、欲望に火をつけられ、生命の摂理に対する裏切りを働くか働くまいか最後の一瞬を迎えていた。どうせならちょっとくらい触っておいてもいいんじゃないか?『おいで…だっこしてあげるよ…』その言葉は口元まで出かかっていた。抱きかかえた小さな身体をゆっくりと弄って園児服をめくりあげ、子供がそのくすぐったさに身をよじるところまで想像して全身の毛が逆立った。今それが可能なのだ。今それが可能なのだ。今それが可能なのだ!すると目の前の園児が息をはずませて部屋のある一点を指さして言った。「ねえねえ、おじさん、これなあに?」
部屋の中にぽつんと置かれているのはつるりとした木の十字架だった。男はこの十字架を購入したその日から何故かこの光景にひどく見覚えのあるのを不思議に思っていた。そして戸口にひもをかけて何度も首を括ろうとした事も思い出された。…そしてずっと昔に既にそうやって幾度となく死んだような気がしているのだった…天使のような幼児に対してこのような暗い日々しか持たぬ自分という存在が殊更恥ずかしいように思えた。「それは十字架だよ」「じゅうじか?」「そう、神様の…」男は教理上の説明を省略して続けた。「昔ここで」男は十字架を指さして続けた。「この十字架で、死んだ人がいるんだ」幼児は大人が戸惑うほどに大きな目をさらに広げてじっと十字架を凝視して言った。「ここでしんだひとがいるの?」意味が通じていないような気がしたが男は受け流し、微笑んだ。「うん、ずっと前からいるんだよ」「その人ずっとしんでるの?ずっとずっとここで死んでるの?ずっとこのじゅうじかにいて…かわいそう…かなしいよ…」全く唐突に紺色の園児服に涙が、そして鼻水までもが零れ落ちるのを見てさすがの半魔物男もたじろいだ。「大丈夫だよ、もう復活して生き返ったから、ほら、鼻かんで」
魔物になりかけた男は何かに打たれたように部屋の中に身じろぎもせず座していた。若夫婦は顔を赤らめながら子供を引き取りに出向いて来た。それからほどなくして…時節が変わるころには彼らは何処かへ引っ越していった。イスカリオテのユダは裏切りの素性を本性として持ち合わせていたのだろうか?生命摂理への裏切りの本性…これに忠実であるということはすなわち自分以外の全てを裏切るということだ。一方キリストのそれは自分を捧げても自分以外の全てを愛するということだ…愛というものは配慮であると何かの本で読んだと男は思った。
…愛はその実、慈愛ではなく単なる根源的配慮なのだと…。
教会へ久しぶりに足を運ぶと豚女はちゃっかり現在の、若い司祭と関係を持っていた。それを隠そうとするものだから余計に周囲にばれてしまい、その司祭は移動させられ、豚女も後を追うように教会を去った。実際にはかの園児にも豚女にも指一本触れなかったことを男は当初どこか誇らしく思っていた。だが男の人生は相変わらず孤独であった。気を取り直してついに…あの手この手で知り合った許容範囲内の女と幾度か付き合ってみたものの現実のセックスは彼の夢想とはかけ離れており、恋もすぐに下火になって女たちも豚女同様に別の相手を見つけて振り向きもせずに去ってゆくのだった。射精前の興奮状態にある時の彼は内心悔やんでいた。自分が自分の求めるものに対して手を伸ばさなかったことを悔やみ、あの時の子供に手を出さなかったこと、チャンスを失ったことを悔やみながら達した。しかし同時にその性処理の済んだ一瞬後には、このような愛の正反対…即ち愛すべき対象への配慮の足りない残酷な夢を抱く自分を嫌悪し、𠮟りつけるのだった。凌辱されるのを望む子供など古今東西何処にも居ない、子供という存在を本当に「愛して」居るなら子供の望むべき愛を与えるのが配慮というものだ、だとすればこれでよかったんだ、子供に手を出さなくてよかったのだと彼は自分に毎日言い聞かせては神に祈った。射精前と射精後でほとんど全く思想を変える自分に心底うんざりもしていた。神様、自分を神に背かせないよう見守っていてください、自分は本当の罪人です…しかし皮肉にも後の人生に於いても子供に対して愛想のいいこの半魔物男は子供と接する機会が必然的に生じ、その都度彼は悪魔の囁きを聞き、自分の本能を満足させるべく子供に触れる一歩手前のところまでいくのだった。だがそのたびに…かの園児が十字架を見て涙を流す光景が頭の中に強烈な光を帯びて浮かび、情欲に勝る何かが自分自身にさえ宿っていることを人を超えた存在から知らされるような心持がして男は魔物の手を引っ込め、自らを諫めて神にひたすら祈るのだった。
それは一般常識を超えた視点から見れば正真正銘の秘められた殉教であった。
如何なる拷問にも劣らぬ魂の試練に生きている間ずっと挑まされ、その実人生の全てをかけて耐えるよう聖なる何かから促されていたのだ。男はまさに、生命摂理への裏切りという本性を背負ったまま情欲という業火に焼かれ、人生を精魂尽き果てるまで歩んだのだった。いつしか男は年老い、いよいよ隠遁者のそれとなった眼差しには裏切りを耐えた者にだけ宿すことの可能な聖なる神秘の光が瞬いていた。ユダとならなかったユダ…無論そのような内的業績に気付く人間は一人も居ないまま男はあっけなく無名の生を終えた。
焼けるような渇きを一生の間耐え抜いた死後の男、その魂は、はや聖者にならんとしていた。男の魂にはこの世で一番醜いものと一番聖なるものとが同居していたのだ。彼の内部にはユダとキリストが居た、悪魔と聖霊とが居た。今やそれが現世でした夢想のどれよりも仲睦まじく幸福に合体しているのだった…二面性…それこそがこの男の本性であったのだ。「見てごらんよ」霊魂と化した男は無数に輝く星を見上げながら空に浮かんでいるとき、聞き覚えのある…男とも女ともつかないあの声を聴いた。声は続けた。「あの星たちはね、君が守った光なんだ、君が配慮を実行したお陰で、君が自分を制して何もしなかったお陰で救われたたくさんの子供たちの霊魂なんだよ」男はその声を聴きながら体無き身体で静かに涙していた。何故自分がこのような不毛な繰り返しの中をここに至るまで生かされ続けたのか、何故自分が裏切りの神秘を背負わされたのか等という問いかけはしなかった。何故なら…最早何処までが自分で何処までが他人かの境目が、この聖者たる男には識別できなくなっていたからだ。自分の人生とはすなわち他人の人生であったし、他人の苦しみさえ今のこの男自身の苦しみであった。男は涙を拭こうと手を伸ばして最早手が無いということに気付いた。男は自分自身を確認しようとしたが自分自身というものさえも全く確定出来ないことに気付いた。遠くに見える星々であるところの子供たちの昇華された魂も、遥か下方に広がる暗い地面も…その穴から顔を出す子供たちの未だ浮かばれぬ霊も、そのすべてから生え出でる枝葉が自分に繋がっているという事を男はようやく理解していた。あれらはすべて自分自身でさえあったのだ…。すべてが自分だったのだ…。男はさらに自分とは何かを見出そうとして進んでいった。葉脈のように全ては連鎖しており、その視点に立ってみて初めてすべてがひとつの生命体…非生命体であり生命体であったことを男は魂と化したその心で深く理解した。魔物になりかけた聖者は光り輝く魂のただ中でにっこりと微笑み、ついに全てと融合し、力強く波打ちながら神の方角へと勢いよく前進したのだった。