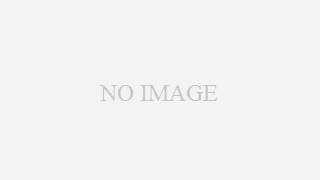人類の贖いが行われてから幾世紀か過ぎ去ったころ、氷の覆う石畳の街に一人の見習い修道士がやってきた。彼も祈りの生活に入るべく共同体の門を叩こうとしたがその時王宮の向こうの空から一筋の光が差すのが見えた。あの光の筋に寄り添うように祈りの生活を行えたらどんなにいいだろうか…!この想いは予想外に彼を猛々しくさせ、ついに見習い修道士は共同体の規律や紹介状までもをかなぐり捨ててその光の柱まで走っていった。光の柱は天から地へと一直線に差しており、その近くに異教徒の立てた神殿の塔がそびえ立っていた。彼は無我夢中で川の水を汲んでその塔を洗い清めると裸足のままそこへ登り、唐突にその街外れの古の塔で祈りの生活を始めた。天から降りる光の中を天使たちが行き来するのが彼にだけはまざまざと見えていたのだ…しかし人々は彼が何を以てして塔の上で生活を営むのか、はじめのうち誰も理解出来ずにいた。
幾年かが過ぎた、見習い修道士は世間からも教会組織からも見捨てられるのかと思いきや、いつしか街の聖者とあがめられていたのだった。一時は異端とされて教会側から追い出されそうにもなったが彼があまりにも素直に塔から降りてきたために、そして彼を聖者と呼びならわす市民の反感のあまりの凄さに司教までもが折れ、とうとうそのまま塔に住むことを教会のお墨付きとして許したのであった。聖者となった見習い修道士が個人的に観ている光の梯子を行き来する天使というのを…一体全体教義上どのように解釈するかを考えるのだけが専ら、教会の仕事と化していた。街外れの古の塔に住む聖者を今では誰もが意識し、彼の居ることを誇りにさえ感じていた。街の風潮は変化し、世俗に居ながらにして高い塔に籠る彼の暮らしを尊んでか、知識階級の老人なども塔に住み出し、それに感化されてか貴族階級もまた自らの箱入り娘等を屋敷に増設した塔に半ば幽閉しながら純血に育てるという教育法が爆発的に流行り出した。悪い虫がつかないように、無意味に妊娠して家名を汚さないように、性的堕落に陥らないようにという願を込められて塔に住む娘たちは狭く冷たい石の塔の一室に閉じ込められ、従者が日々食事や排泄用のおまるを手に長い階段を行き来する光景がこの石畳の街では日常的に見受けられるようになった。中には…娘の脱走を阻止するためか、目のくらむほど高い外側の、手すり等の一切無い階段を使わねば登頂部へ行けない仕組みになっている塔もあり、運の悪い従者が足を滑らせて頓死したりする事態も勃発した。このような惨事の発見が遅い場合には塔の中に居る箱入り娘当人さえも餓死しかかっていたり糞尿の中で呆然としていたりというさらなる珍事が引き起こされた…それでも街ではさかんに塔が建造され、庶民は高い塔に住まう尊き人々に無意識に心を引き寄せられてか常に空の方に首を傾けながら歩いていた。
ある時、聖者と名高いこの見習い修道士の目には光の柱が見えなくなってしまった。夕闇のせいでないことは確かだった。幾度自分の瞼をこすってみても駄目で、動揺した彼は衣服を掻きむしって裸になると塔の窓から身を乗り出して叫んだ。天使たちよ何処ですか?どうしてお見捨てになったのでしょうか?答えは無く、彼の声は石畳に反響して街々にこだました…。その時少し離れた塔の窓が開かれるのが見えた、その窓辺に置かれた蝋燭の灯りが一人の娘の顔を赤々と照らし出し、あっと思う間もなく彼女が素裸で微笑んでいるのが見えた。距離があるとはいえ塔と塔との間には何の隔たりも無いので意外なほど互いがよく見えるのをこの見習い修道士はその時初めて知ったのだった。彼女の滑らかな肌、燃えるような赤い髪、小さく突き出た紅色の乳房がありありと…元々天使の行き来していたであろう光の柱の近くに妖しく浮かんでいるのだった。同じ時空間とは言えど天使のそれは既に見ることさえ叶わない一方、天使以上の美しさを誇る魅惑的な娘が彼に今微笑みかけている。見習い修道士は急いで窓を閉めると悪魔退散の念祷に専念しようとした。…だが彼はその代りに射精し、自責の念に駆られて明け方まで祈っていた。悪魔よ悪魔よ立去れ、神よ神よお助け下さい。
朝になって恐る恐る窓を開けてみるとやはり娘は居て、ちょうど朝日を浴びるその姿は世界から切り取られたかのように浮き出て見えた。見習い修道士は自分の未熟さを心から悔やんだが赤毛の娘に微笑まれると今まで自分が何をやっていたのかさえ忘れてしまいそうになるのだった。気付くと娘は貴族特有の仕草で非礼を詫びる姿勢をとっていた。どうやら昨日裸で窓辺に居たことをジェスチャーで伝えているようだった。聖者様ごめんなさい、あなたとを見てみたいといつも思っていました、私はあなた様に恋をしていました、至らぬ私をどうかお許しください…赤毛の娘の言葉がその仕草に込められていた。それを目にした彼は余計に自分を恥じた…彼女を内心悪魔だと罵った事、そう罵りながらも赤い髪に反転して輝く素肌や生娘特有の張った乳房を思い浮かべて卑しくも自慰したこと。塔と塔との間にはかつて天使の柱が見えていて、それが為に彼女を知る事さえ無かったのだが、今は天なる目隠しが空間から取り除かれたがために窓を開けさえすればこの現実的に美しい赤毛の娘と対面してしまうこと、見とれてしまうであろう事を彼は恥じた。表立って娘を舐め回すように見る等という事をするくらいならさっさと塔の窓から身を投げる方がマシだと見習い修道士は思っていた。それを避けるためにはなるべく彼女を見ないように生活しなければならない。いよいよ苦行と化したこの登塔者である隠遁者の奇妙な日々が始まった。欲望を抑えようとすればするほどに欲望は膨れ上がり、彼を責め苛むのであった。
朝起きると肩書だけは聖者たる彼は窓をそっと開け、赤毛の娘が居ないのを確認するとそこから光の柱が見えるかどうかを試す。排気口としても窓は開けておかねばならないという実質的な事情もあって、娘を見ないように過ごす事は実際かなり困難であった。この困難さ故に内心娘を憎みさえした。心底邪魔だとさえ思った。娘の事を意識しないようにしてみても神の前には個の生命等が塵芥に等しいのと同じくらい無力な試みであって、彼の陰茎は彼の真意に反して始終勃起していた。この興奮の為に黙祷しにくく、黙祷にしくいが故に…神を愛する祈りを捧げにくいという理由で彼はまた娘を、殊更その美しさを恨み、息を弾ませながら精液を出し終えると同時に、今度は隣人を悪魔だと罵った罪に涙するのであった。
神に反している…そう思ってはいても心は娘の方へ飛んでゆくのを、聖者とは名ばかりの見習い修道士は切実に感じるようになった。いつしか彼は神に対して厚かましくなり、娘を盗み見るようになった。窓の端に立ち、丁度隠れる位置に彼は居て陰茎を握って向かいの塔の娘を見るのだった。気分が高ぶった時には窓の外へ、少しでも娘の近くへ射精するつもりで精液を外へ飛ばす事さえあった。自分のこのような獣の行いを再三恥じ入り、次にやったら自分は今度こそ自殺するのだと決めるのだが…決意が大きければ大きいほど赤毛の娘を欲する情動は増し、一昼夜経つと元の木阿弥という状態に陥っていた。
天使の梯子を急降下している見習い修道士と相反するように、一方では奇妙なことも起きていた。赤毛の娘は当初裸であからさまに蠱惑的な視線を送っていたのに、今では窓の外へ顔を出すときにはきちんと服を着て、時に祈っている事すらあった。…この事情を第三者にいくら説明しても不可思議という言葉以外には該当しないであろう。不可視の天使の梯子を間に両者は精神的肉体的堕落と精神的上昇を体現するが如く、最早天と地を上り下りしているのは天使ではなく二人の登塔者であるのだった。
こういった当事者にしか理解出来ぬ内的事情から、赤毛の娘は日が経つにつれ好奇心旺盛な少女から聖女のような変貌を遂げ、聖人と誉れ高い見習い修道士は恥ずべき肉欲の捉われ人へと相成っていた。季節が移り替わる頃、見習い修道士はついに気が付いた、自分は聖者どころか見習い修道士ですらないことを…。赤毛の娘は修道女のように、最近では始終祈るようになっていた。彼は既に隠れることさえせず、何の躊躇いもなくじっと娘を見つめていた。赤い髪の毛がふわりと風になびくと同時に娘の顔に涙が光るのが見て取れた…。夕闇の中、娘の頬に二筋の涙だけが宝石のように光り輝くのを見てようやく彼は悟った。何故この赤毛の娘が窓の外を見て泣いているのかを理解していた。彼女は今天使を見ているのだ。見習い修道士の視線に気が付いた娘は…おそらく天使の梯子というこの世ならざる光の柱越しに、いつものように微笑んで、しかしちょっと悲し気に会釈したのだった。男はかつてこの娘を、祈りを邪魔する悪魔だのと罵った自分を呪った、悪魔は自分なのだ。彼女は罪から立ち返った、しかし自分は罪に溺れた。胸中を見透かされたかのように感じて彼は恥じつつ、何かに耐えるように窓辺に立っていた。そうやってしばらくの間二人は初めて見つめ合った。天使の柱越しに男女は見つめ合った。それがこの世の尺度で換算したらどの位の時間であったのかは定かではない、その日を境に彼らの間に共通の秘密が交わされたのだった。立場はその実逆転したものの二人は恋に落ちていた。
夢想と現実の狭間で幾度も抱き合っては口づけを交わし、天使の柱の話をする…。それは確かに彼等各々の妄想でしかなかった…。だが現実にも窓は一日中開いたままとなった、北風が吹き付け、雪が降っても二つの塔の窓は開かれたままだった。そこに二人が堂々といつまでも見つめ合っているのを、この石畳の街の口さがない人々は一斉に噂し始め、夜になると二人は綱を塔と塔の間にかけてそれそれに行き来して逢瀬を楽しんでいるだの、あの聖者は魂を身体から抜け出させて娘の所へ忍んで行っているだの、もうあの赤毛の娘は聖者の子を身ごもっているだのと散々に囃し立てた。
聖者と呼ばれているとはいえ、教会の肩書では彼は共同体へ行かずに塔へ籠った見習い修道士のままである。教会は街に広がる不埒な噂によって神が汚されるのを防ぐため、早速彼の元へ出向いて彼を塔から引きずり下ろした。さる貴族の娘であった件の赤毛の娘もほどなくして塔から降ろされ、彼女の親族が金に物を言わせて血眼になって愛する我が子を救い出そうと教会に持ち掛けても撥ね退けられ、ほどなく見習い修道士を誘惑したかどで赤毛の娘は異端審問に問われる事になった。二人の公開審問は塔と塔の狭間…ちょうど天使の行き来する光の柱の場所にて行われ、おびただしい数の群衆が集結して決議を見守った。だがこの不謹慎極まりない下品な噂が教会の教えと合致しているはずもなく、審議の始まる前から二人の有罪は決定していた。高僧は声高らかに聞いた『何故塔の外を見ていたのか』赤毛の娘は答えた『天使の柱があるからです、ちょうどこの場所に天と地を繋ぐ光の柱があるのです、私もそれを見ていたし聖者様もそれを見ていたのです』この答えに、はや異端者として縛られていた見習い修道士は打ち震えた。やはり彼女こそは聖女だったのだ。二人の目と目が今まで一番近い物理的距離で丁度合い、その時に燃えるような熱量が確かに周囲に広がった。異端者の烙印の押された見習い修道士は答えた。
『私たちはかの贖い主と同じように死ぬのです、でも私は愚者に過ぎず、あなたは聖女です、聖女というものは世の穢れを知らぬから聖女なのではなく、穢れから立ち返るマグダラのマリアの如き復活者を讃えるための称号なのです、塔の中に閉じ込めたからと言って誰もが清らかにはなれないのです、しかし彼女は聖女です、彼女は罪から立ち返りました、彼女は聖女です!』これ以上無い愛の告白に群衆はどよめいた、やっぱり出来ていやがったんだと野次が飛ぶ中、審問官は二人は絞首刑と定め、次の瞬間には用意されていた首括り台の布が取り払われ、群衆は歓声をあげた。
一刻も経たぬ間に判決の下された二人はそれでも胸の高鳴りを抑えきれずにいた。現実味の無いまま処刑台へと足をかけるその時、聖女たる赤毛の娘が叫んだ。『ああ、天使が降りてくる、炎の矢を携えて天から舞い降りて来る!!』この言葉に呼応してか堕落した見習い修道士までもが唐突に光の柱を再び見た。まさに光の柱のただ中に処刑台は設けられ、そこで娘と死ねることを心から嬉しく思った。その光の柱の遥か頭上から…赤毛の聖女の言う通り、赤い天使たちが降りてくるのがはっきりと見えたのだった。場を取り仕切っている審問官は手を振りかざして群衆を制した。『異端者の言う言葉を真に受けるな!塔に登る生活をすることもこれからは異端と見なす!』しかし聖女となった娘の赤い髪の毛から唐突に劫火が噴き出たのを誰もが目にしていた。わっと叫んで一同が逃げようとしたその時にはもう大多数が火の海に飲まれていた。見習い修道士だけはこの炎を厭わなかった。赤い髪の聖女と彼は見つめ合ったまま甘い炎に全身を舐められながら喜悦の死を遂げたのだった。
…当時としてはこの不審火によってとんでもない数の犠牲者が出たことから、以後、塔に登って生活する者即ち登塔者の修道様式は厳禁となった。果たしてこの炎が天からの罰として下されたものなのか、はたまた二人の恋の炎なのか、神の火で燃え盛る愛の十字架を示す現象だったのか、恋あるいは情欲と宗教心及び隣人愛の融合により生じた禁断の炎だったのかは…光の天使の柱同様、当人たちを含め誰にも解き明かされることは無かった。
※この小説はフィクションです、実際のロシア正教及びいかなる宗教団体とも無関係な視点から書かれたものです。